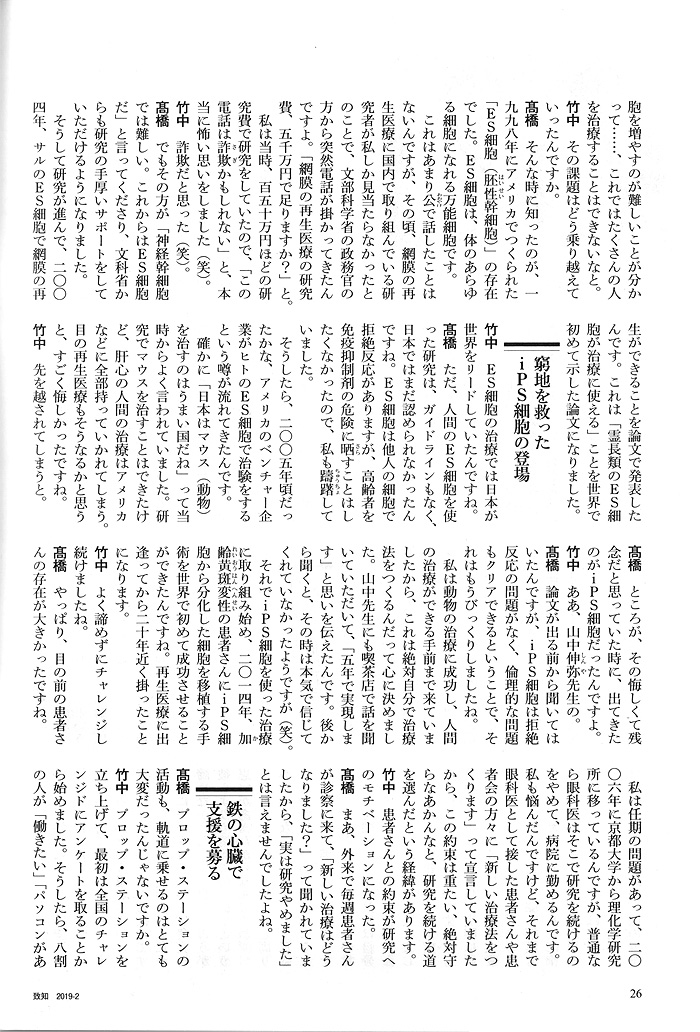�v�m�Q�����@�����R�P�N�P���P�����s���]��
���W�@�C�C����
�Βk�@�g�������^������
�i�~�˂���������コ��Βk
���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���W�@�C�C����
�Βk
�g�������^������
�R���s���[�^�ȂǍŐV�̉Ȋw�Z�p�����p�����Ⴊ���ҏA�J�x���ɓ�\�N�ȏ�ɂ킽���ĕ������Ă����v���b�v�E�X�e�[�V�����������̒|���i�~���B�����̊�Ȉ�Ƃ��Ŗڂ̔Y�݂������l�X�Ɍ��������ƂƂ��ɁA�@�o�r�זE��Ԗ��ɈڐA�����p�𐢊E�ŏ��߂Ď������Đ���Â����[�h���鍂�����㎁�B���̒��̈�w�╟���̏펯�ɒ��݁A���Ȃ������ł�������l����荇���A���̋C�C�����̐l���A�����čK���ȎЉ����������q���g�[�B

��������
���������J���@�l
�����w�������Ԗ��Đ����
�����J���v���W�F�N�g
�v���W�F�N�g���[�_�[�^��Ȉ�
�����͂��E�܂���\���a36�N���{���܂�B���s��w�w��w�����ƁA���s��w��w���t���a�@�ł̋Ζ����o�āA�����V�N�A�����J�E�\�[�N�������ɗ��w�B�A����A��Ȉ�Ƃ��Ċ��҂ƌ��������Ȃ���A���s�l�w��w���t���a�@�T����ÃZ���^�[�������A�Ɨ��s���@�l�����w�������Ə�����ւ��A�Ő�[��Â̌����Ɏ��g�ށB

�|���i�~
�Љ���@�l
�v���b�v�[�X�e�[�V����������
�����Ȃ��E�Ȃ݁\���a23�N���Ɍ����܂�B�_�ˎs���{�R���w�Z���ƁB24�̎��ɏd�ǐS�g�Ⴊ�����̒����������������ƂŁA�Ⴊ������ÁE�����Ȃǂ�Ɗw�B�Ⴊ���Ҏ{�݂ł̉��Ȃǂ̃{�����e�B�A�������o�āA�����R�N�A�J�x�������u�v���b�v�E�X�e�[�V�����v��n�݁B�Ⴊ���҂̃p�\�R���̋Z�p�w���A�ݑ�[�N�Ȃǂ̃R�[�f�B�l�[�g���s���B�P�P�N�G�C�{�������N�x����܁A14�N������b��܁B�����Ɂw���b�L�[�E�[�}���x�i�V�Ёj�Ȃǂ�����B
�v���Ǝu��
�����������l
�����@���傤�͑Βk�Ƃ������Ƃł����A�����̂悤�Ɂu�i�~�˂��v�ƌĂ��Ă��������܂��i�j�B
�|���@�}�Ɂu�|������v���ČĂ�Ă��ˁi�j�B�����u���コ��v�ł�点�Ă��炢�܂��B
�����������߂ďo�������̂͊m����Z��Z�N�A�_�ˎs����ÃZ���^�[�����s���a�@�̗ϗ��ψ���ł�����ˁB���コ���@�o�r�זE���g�����Ԗ��̍Đ���Âɂ��Ĕ��\���ɗ����āB
�����@�����A�����ł����B
�|���@���̎��A���コ��͂����ɂ������҂Ƃ��������Ŕ��\������Ă�������A�u������ƈ��݂ɍs���܂��H�v�Ƃ������Ă͂����Ȃ��l�ȂƎv���܂����i�j�B
�����@����͂����ł��@�ْ����܂����́A�ϗ��ψ���̔��\�́B
�|���@���̎��ɉ�����̂�……�B
�����@�i�~�˂����m���Ă���A�����s���̊W�̕��ɁA�u���Љ�킹�����l�����邩��v�ƗU���ĎQ���������݉�̐Ȃł��ˁB���̈��݉�ɍs������A�u����A���̔��̖т̐l�͂ǂ����ʼn�������Ƃ�����B�ϗ��ψ���̎����v�ƁB����Łu���A���Ȃ́H�@���̂��������������܂́v�Ƌ������i�j�B
�|���@����R��A��i�j�B���̐l�ɂ��܂��A���̔��^�����͂悭�o���Ă��炦��悤�ł����ǁB
�ł��A���̈��݉�̏�ł����ɂ��݂��ł���������ł���ˁB
���͓�\�N�قǑO�ɎЉ���@�l�v���b�v�E�X�e�[�V�����v�𗧂��グ�A�R���s���[�^�ȂǍŐV�̉Ȋw�Z�p�����p�����`�������W�h�i�Ⴊ���ҁj�̏A�J�x���𑱂��Ă��āA���コ��͂��o�r�זE���g�����Ԗ��̍Đ���ÁA�����Ċ�Ȉ�Ƃ��Ď��o�Ⴊ���҂��T�|�[�g������g�݂�����Ă����B
������A���ɂ͐��コ��ƗF�B�ɂȂ肽���A�l����m�肽���Ƃ����C��������������������ł��B
�����@�����i�~�˂��Ǝ��ۂɘb���Ă݂Ăт����肵�܂����B���܂ł����A�h�s�����p�����Ⴊ���҂̏A�J�x���͍L���m���Ă��Ă��܂����A�i�~�˂��͂�������\�N���O����l���Ď��H���Ă����ƁB���o�Ⴊ���҂̎��Â�T�|�[�g�Ɍg��鎩�����A�ŏI�I�ȃS�[���Ƃ��āA�i�~�˂��Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��������ȂƎv���Ă�����ł��ˁB
����`�������W�h��Ƃ͢�Ⴊ�������l���\���V�����Č�the challenged (����Ƃ����g����ۑ褒��킷��`�����X�⎑�i��^����ꂽ�l)����ꌹ�Ƃ���Ⴊ�����}�C�i�X�Ƃ̂ݑ�����̂łȂ���Ⴊ�������䂦�ɑ̌�����l�X�Ȏ��ۂ��������g�̂��ߤ�Љ�̂��߃|�W�e�B�u�ɐ������Ă�������Ƃ����z�������ߤ�v���b�v��X�e�[�V������1995�N������Ă���ď́B
�|���@����A�ォ��ڂ����b���܂����ǁA����͎����l�������Ƃł͂Ȃ��A��������R���s���[�^����g���āA���Ƃ������Ď������悤�Ƃ��Ă����`�������W�h�̕��X���狳���Ă��������ł��B���͎��̓p�\�R�����Ȃ�ł���i�j�B
�F�̗͂����킹���
�V�����Љ�������
�|���@�Ƃ���ŁA���コ���g��ł��邉�o�r�זE���g�����Ԗ��̎��Â͂��܂ǂ��܂Ői��ł���̂ł����B
�����@�����ŋ߂̓����ł́A��Z��l�N�Ɋ��҂���{�l�̂��o�r�זE���g�������Âɐ������A���܂͑��l�̂h�o�r�זE���g�������ÂɎ��g��ł��܂��B�ł��A����Ŏ��ۂ̎��Âւ̓��������J����Ƃ����킯�łȂ��A�܂����l�̂��o�r�זE���g�������Âŋ��┽�����N���炸�A�u���S�ł��v�Ƃ������Ƃ��������i�K�Ȃ�ł��B���ꂩ�炪�{���̎��ÂÂ���ɂȂ�܂��B
�|���@���ꂩ�炪�{�Ԃ��ƁB
�����@�����A���o�r�זE���g�������Â̌����́A���܌���̌����������ꂼ��̂Ƃ���ł�����Ƃ���Ă���Ă��āA���͎��͂���܂�ւ���Ă͂��Ȃ���ł��ˁB
���Ⴀ��������Ă��邩�Ƃ����ƁA�_�˃A�C�Z���^�[�ŎЉ�Ȋw�n�̎d���Ɏ��g��ł����ł��B�Ⴆ�A�J�����i�ގ����^�]�Ԃ��A�ǂ�����Ύ��o�Ⴊ���҂̕�������I�A�D��I�Ɏg����悤�ɂȂ邩�A���̂��߂ɂǂ�Ȏd�g�݂�[�����������炢�����Ƃ������������v�悵�Ă��܂��B
�{���A�]���̎Ԃ��^�]���邱�Ƃ��ł��Ȃ����o�Ⴊ���҂����A�����^�]�Ԃ̉��b����ԂɎ�ׂ����Ƃ����v���������ł��ˁB
�|���@�{���ɂ��̒ʂ�ł��ˁB�ŋ߃v���b�v�E�X�e�[�V�����ɒ��ԓ��肵�Ă��ꂽ�Ⴂ�q�́A�S�ӂŔ]����ჂŁA�Ԉ֎q�Ȃ�ł����A�p�ꂪ���ӂł��ĂˁB�p�\�R���≹�����u�Ȃǂ��ǂ�ǂp���āA���̍u����L����|��d�������Ă���Ă����ł��B
����ŁA���ܔނƎ��́A�Ԉ֎q�̎����^�]�Ŕނ��I�t�B�X�̒������R�ɓ�����悤�ɂ��邱�Ƃ����ɂ̖ڕW�ɂ��Ă����ł���B
�����@�����A�����^�]�ŁB
�|���@���ہA�A�����J�ł͎����^�]�̌������������i��ł��āA�L�����[�o�b�O�������^�]�ł��q������s�@�܂ňē�����Z�p���l�����Ă��邻���ł��B����͎��ۂɂ��̌����Ɏ��g��ł���h�a�l�̕��̍u���ŕ����܂����B
�ŁA���v���̂�B�ڂ̌����Ȃ��l�������Ԃ����Ă�����A��Ɏ��̂̋N����Ȃ����̒��ɂȂ��Ă��邾�낤�Ȃ��āB�s����Ȗڂɗ����ĉ^�]����Ԃ������������ʎ��̂͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��B
�����@�Ȃ�قǁB���̔��z�A�l�����A�����g�킹�Ă��炢�܂��B
�|���@������A�h�a�l�̕��Ɛ��コ��̌����A����Ɏ������̂悤�ȃ`�������W�h�̎x��������Ă���`�[�������������ŋ��ŁA�S���V�������̒��������Ȃ����Ǝv����ł���B
���������˂�
���������N�����
�|���@���コ��́A���Ƃ��ƈ�ÂŊ��҂�����~�������Ƃ����悤�ȑ傫�Ȏu���������̂ł����B
�����@�����A������w�̓��ɐi�͓̂��ʂȖړI���������킯�ł͂Ȃ��āA���e����u�푈�ɂȂ��Ă���҂͐H�ׂĂ�����v�u���ꂩ��́A�����������ŐH�ׂĂ�����悤�ɂ��Ȃ����v�Ƃ����ƌ����Ă�������Ȃ�ł��ˁB
�Ȃ̂ŁA��㔪�Z�N�ɋ��s��w��w���ɐi��ł�����A�e�j�X�ɖ���������X�𑗂�A��Ȃ���ɑI�̂��A�u��Ȉ�͖�̌Ăяo���Ȃǂ����Ȃ�����A�ƒ�Ǝd���𗼗��ł��������v�Ƃ������������ɓI�ȗ��R�ł����B
�|���@������������ł����B
�����@�����B�����́A��w��ʂ��āA�����傫�Ȏd������肽���Ƃ͑S�R�l���Ă��܂���ł����B
�����A��w���ƌ�Ɍ��������]�_�o�O�Ȉ�̕v���A����ܔN�ɃA�����J�̃\�[�N�������ɗ��w���邱�ƂɂȂ��āB���̎��A���͊�Ȉ�Ƃ��ĕa�@�ɋ߂Ă����̂ł����A�v���Z�p�I�Ɏ�`����Ƃ��������ŁA�c����l�̖���A��ė��w�ɂ��Ă�������ł��B
����������A�����̃\�[�N�������́A�]�̍Đ���Â̎�A�ޗ��ɂȂ�u�_�o���זE�i�����ڂ��j�v�𐢊E�œ�Ԗڂɔ��������Ƃ���ŁA����܂ł̏펯���Ő�[�̍Đ���Ì����Ɏ��g��ł�����ł���B
�|���@�Ő�[�̌����ɐG���ꂽ�B
�����@���̎��ɁA�������Ƃ���ڂ͔]�̒����_�o�̐�[�ɂ���܂�����A���ꂪ�Đ��\�Ȃ�ڂ̖Ԗ��̍Đ����ł���͂��B������Ȃ��ڂ̕a�C�����Âł���̂ł͂Ȃ����ƍl������ł��B����͎������łȂ��A��Ȉ�Ȃ�N�ł��l�������Ƃ������Ǝv���܂��B
��Ȉ�̎������܂��܃\�[�N�������ɍs���āA�����A�Ő�[�̔]�̍Đ���Ì����ɏo�����Ă��܂����B���܂����m���Ă����Ȉ�͎������Ȃ̂ł͂Ȃ����A���������Ȃ���A�ڂ̍Đ���ÁA���Â͌ܔN�A�\�N�x��邩������Ȃ�……�B�����v�����̂��A��A�̌��������̎n�܂�ł��ˁB
�|���@��̎g�������ˁB
�����@�͂��B��Ȉ�Ƃ��ē��X���҂����f�Ă����̂ŁA�u���Ƃ������Ă��������ȁv�Ƃ����g�����͂����Ǝ����Ă��܂����B
���ƁA�������������悤�ɁA�m���ɑ傫�Ȏd������肽���Ƃ͎v���Ă��Ȃ�������ł����A�u�V�������Ƃ���肽���ȁv�Ƃ͏�Ɏv���Ă��܂����B����͂��ܐU��Ԃ�ƁA��̉e�����Ǝv����ł��B
���܂��o���Ă���̂��A���w���̎��ɔN���̍g���̍�������Ă���ƁA�ꂪ�u���̉̎�͎����ʼn̂��������H�@����Ƃ������̂��Ă��邾�����H�v�ƁA�����Ă��āA�̂𔒕��ł������̎肪�o����u���̐l�̂��ˁv���Č�����ł���B����Ŏ��́u�V�������Ƃ�����l�͈̂��v�Ƃ������Ƃ����荞�܂ꂽ�i�j�B
�|���@�ł��A�ǂ����Đ��コ��̂��ꂳ��́u����l���̂��v�ƍl����悤�ɂȂ�����ł����B
�����@���[��A���ł��낤�B��͕��ʂ̎�w��������ł����A�����Ƃ���ɂ��ƁA���\�A��ԁi�킪�܂܁j�Ȑl�ŁA�̂���u�l�Ɠ������Ƃ͌����v�Ƃ������i�������悤�ł��B���w�Z�ɒʂ��Ă��鎞�ɁA��l�����搶�ɔ��R���āA���̎��Ƃ����͉��ƌ����悤�Əo�Ȃ������ƁB
�|���@�����A�m���ɂ��̂��ꂳ��̌��͗���Ă����ˁi�j�B
�����@��ԂȂƂ���ɂˁi�j�B
�����Ă��邾����
�������
�����@�i�~�˂��́A�ǂ�Ȃ��������Ō��݂̊����Ɍg���悤�ɂȂ�����ł����B
�|���@���ܕ�e�̘b���o�܂������ǁA���ɂ������悤�ȑ̌���������……�B���͈��l���N�ɐ_�˂Ő��܂ꂽ�̂ł����A���͋��s�鍑��w�o�g�ŁA���͑��Ƃ̏d���R�[�X����݁A��͕�ŌF�{�̋��Ƃ̂���l��������ł��ˁB
�Ƃ��낪�A���̕�͋��Ƃ̏o�ɂ��S�炸�A���e�ƒ��j��������i�����Ȃɍ����Ĕ����t���̗�����H�ׁA���̑��̉Ƒ��͎��f�Ȑ���������A�Ƃ����悤�ȓ����̕����������Ȃ�������ł����āB
�q��Ăł��A�����鋃���ŃM���[�Ƌ����ƁA�N���Ă����ς��������Ȃ��Ƃ����Ȃ�����Ȃ��ł����B������J��Ԃ��̂�����Ȃ����������݂����ŁA���L�Ɂu������i�~�������Ă���B���͋N���オ���ē�������Ă��邪�A�v�͂��̉��ŐQ�Ă���B�i�~�A���O�͒j�ɕ����Ȃ����ɂȂ��v�݂����Ȃ��Ƃ������Ă����ł��B
�����@��������e�ł��ˁi�j�B
�|���@�������A�����q����������Ȃ��Ȃ番����܂����ǁA���͋ߏ��ł��q�ϔY�i���ڂ�̂��j�ŗL���������B
����ȕ�ł�������A����ɏ�������^���̂悤�Ȃ��̂ɛƁi�͂܁j���Ă�����……�B�d���R�[�X�����ł��������A������A�J���҂��v���̂��̂��Ȃ�������Ă���p�ɂȂ����V���p�V�[�������A��Ђ̑�������U�������Ƃŋߐ���N�r�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�u�A�J�v���ƃ��b�e����ꂽ��ł��B
�����@���ق���Ă��܂����B
�|���@���̎��A��͂ǂ��������Ƃ����ƁA�u���̒��ɂƂ��Đ��������Ƃ�������B�N�r�ɂȂ������Ƃ͐������v�ƌ����āA���Ԕт𐆂����B�Ȍ�A�䂪�Ƃ͂ǂꂾ���n�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A�����{���ɁB�e�ʂ̉Ƃ�]�X�Ƃ��Ă�������������܂��B
�����������ŁA���̓O���ĉƏo���J��Ԃ��A�����l�Ƃ��t�������悤�ɂȂ��āA�u�_�˂ň�Ԃ̃����v�ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B���肩��́u���{�̔�s�����̑����I�v�ƌ����Ă܂����B
�����@�ǂ�Ȃ��Ƃ�������A�����������ł��傤���i�j�B
�|���@�ł��A���e����́u�����͕n�����v�Ƃ������t���������������Ƃ�����܂���ł����ˁB
����ɁA�������܂ɉƂɋA���Ă��������A���́u�i�~�A���O�������Ă��邾���ł������v�Ɖ������}���Ă���邵�A����u���Ȃ��͂������҂��ɂȂ邩�炢���̂�v�Ɠ{���Ȃ�������ł��B
�����@��Ɏ���Ă��ꂽ�B
�|���@������A�F�B����͂悭�u�i�~�͐�Ɏ��̎q����Ȃ��B�{���̎q��������e�̓i�~�̂��Ƃ�{��v�ƌ����Ă��܂����i�j�B
�l�ɂ͂��ꂼ��
������X�s�[�h������
�|���@�\�܍̎��ɃA���o�C�g��ŏo�������l�Ƃ͑��������āA���Z�͏��ЁB�\�Z�Ō������Ď�w�ɂȂ�����₯�ǁA���̌�̑傫�ȓ]�@�ƂȂ����̂͑��q�̏o�Y�ł����B��\�l�Ŏ������������̖��I���S�g�ɏd�x�̏Ⴊ���������Đ��܂�Ă�����ł��ˁB
�����@�����Ⴊ����……�B
�|���@����ŁA���I��A��Ď��ƂɋA��ƁA�u�i�~�������Ă��邾���ł������v�ƌ����Ă����q�ϔY�̕����A�u�킵�����̑��ƈꏏ�Ɏ���ł��I�v�Ƌ���ł��B���̎q����Ă�A�i�~����J���ĕs�K�ɂȂ邩��ƌ�����ł��B
����͎������㉹��f���Ζ{���ɕ��͖��I�ƈꏏ�Ɏ���ł��܂����������B�����������@�͂Ȃ����Ȃƍl���邤���ɁA�ς��ƑM�����̂��A�u�ǂ�����Ζ��I�Ɗy�����߂����邩�B�������y�����ق���I��Ő����Ă������v�Ƃ������Ƃł����B���ɂ��u�K�s�K�͎��������߂�B�������A���炠����v�݂����Șb�����܂����B�܂����ǁA���͍Ŋ��܂Ŏ��̍ō��̉����c�ł��Ă���܂������ǂˁB
�����@�������S�̎��������ƁB
�|���@�����Ė��I�̌P���{�݂ɒʂ����ŁA�ڂ������Ȃ��A�����������Ȃ��A���_�ɏd���Ⴊ��������ȂǁA������`�������W�h�̕��ɏo�����Ă�������ł����A�����F��������ł���B�z�����Ă����悤�ȁu�������v�Ƃ��u�C�̓Łv�Ƃ��������̐l�͑S�R���Ȃ��B
�Ⴆ�A�ڂ̌����Ȃ����v�w���Ԃ�������������ƈ�ĂĂ����ł��B�����K�˂�Ɓu�Ԃ���
�n�C�n�C�[�����Y��ɏ��ł����ł��ˁB
������A���͂����ȃ`�������W�h�ɏo�����Ďv���悤�ɂȂ�����ł��B���̒��̕������`�������W�h����������Ă����Ȃ�������Ȃ��A�u�������v�ȑ��݂��ƌ��Ȃ��Ƃ��납��o�����Ă���̂��A���������̊ԈႢ�ȂȂƁB�����ƃ`�������W�h���ł��邱�Ƃɖڂ������āA�ǂ��������ł���悤�ɂȂ�̂��l���Ă������ƁB
�����@�{���ɂ��̒ʂ�ł��ˁB
�|���@���ꂩ��A���͖����������ď��߂āA�l�͂��ꂼ�ꐶ����X�s�[�h���Ⴄ���Ƃ������Ƃ��w�т܂����ˁB����͎���������w�ő�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B
�����@������X�s�[�h���Ⴄ�B
�|���@�l�Ԃ͐��܂�ĉ������Œ���悤�ɂȂ�A���ł����Ȃ��āA�Ƃ������Ƃ��펯�̂悤�Ɍ����Ă��܂����ǁA���I�͏�̌Z�������悤�ɂȂ����N��ɂȂ��Ă��A����Ȃ��ǂ��납�A���܂����邱�Ƃ͂ł��܂���B���I�͖��I�̃X�s�[�h�Ő����Ă����ł��ˁB
������l�͊F���ꂼ��A�������ł����ƊJ����������ł��B�u�l�Ԃ͂����łȂ����Ⴂ���Ȃ��v�Ƃ������̒��ɂ���g����A����Ӗ��������s���Ȃ�₯�ǁA���I�̂������ʼn������܂����B
���ƁA�l���x������A�x����Ƃ����W�́A�O���f�[�V�����̂悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��������܂����B���̒��ɂ͎x�����ςȂ��̐l�͂��Ȃ����A�t�Ɏx�������ςȂ��̐l�����Ȃ���ł��B
�x��������������
���̒��ɂ��Ă�����
�����@���̌�́A�ǂ̂悤�ɕ���ł����ꂽ��ł����B
�|���@���I�����܂�A���炭�g�̏Ⴊ���Ҏ{�݂ł̉��A��b�ʖ�Ƃ������{�����e�B�A�����Ɍg����Ă��܂����B���̒��ŁA���������������h�s�����p���A�����Ȑl�Ɗւ��������Đ��������Ɠ����Ă���`�������W�h�̕��ɂ��o��������ł��ˁB
���̈�l���r����ŁA�ނ͍��Z����Ƀ��O�r�[�̎������̉��䂪���ƂőS�g����Ⴢ��Ă��܂����B�����ǁA�d���Ԉ֎q�ő�w�@�ɒʂ��A�R���s���[�^���o���o�������āA�ƋƂ̃}���V�����o�c��������Ǘ��\�t�g�������őg��ƁA�����������q��������ł��ˁB
�����e���u�����̑��q�A�������ł��傤�v�Ɠ�R�j�R���Ă��āA���́u�����A�`�������W�h��������悤�ɂȂ���Ă��Ƃ́A����Ȃɂ��F���ς�邱�ƂȂ��v�Ă������Ƃ���Ɏ������܂����B
�����@�f���炵���ł��ˁB
�|���@����ŁA�r����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��ł���l�������Ƃ���͂����ƁA�u�N�̂悤�ɓ�����`�������W�h��������A����܂łƂ͈Ⴄ�����A���̐l�Ɏc���ꂽ�\����S�������o���A���̐l�����̐l�Ȃ�ɔ[�����Đ���������{�ɂȂ邩����������v���ē`������A�ނ��u���Јꏏ�ɂ���Ȋ������������v�ƌ�������ł��ˁB
�܂��ʂ̏d�x�Ⴊ���̐N�͂���Ȃ��Ƃ������܂����B�u�R���s���[�^�����ł�������������H�@�R���s���[�^������A�A�����J�Ɠ��{�̊ԂɊC�����������āA�����d���̂���肪�ł�����ŁB��������A�l����Ђɍs���Ȃ��Ă�����Ɏd���������v�ƁB����͂��������ƌ����ȂƎv���āB
�������ē����v���������ԂɏW�܂��Ă��炢�A�R���s���[�^�Ȃǂ̉Ȋw�Z�p�����p���ă`�������W�h�̏A�J�x�����s�����̍��c�́A�v���b�v�E�X�e�[�V�����������N�ɐݗ����܂����B�X���[�K���ɂ́u�`�������W�h��[�Ŏ҂ɂł�����{�I�v���f���܂����B���ꂪ�����̎n�܂�ł��B
�����@������������ł��ˁB�u�v���b�v�E�X�e�[�V�����v�Ƃ������O�͂ǂ����痈�Ă����ł����B
�|���@���̊������n�߂鎞�ɁA�r����Ɂu�O���[�v�̖��O���ɂ��悤���H�v���đ��k������A�u�v���b�v�ɂ��悤�v���Č�������ł���B�u�v���b�v�ĉ��H�v���ĕ�������A�u���������O�r�[������Ă������̃|�W�V�����Ȃv�ƁB
�u����A���O�r�[�`�[��������Ⴄ�˂�v���Č�������ł����ǁA�ނ����ׂ���u�v���b�v�v�ɂ͎x���A�������_�A�x���������Ă����Ӗ��������āA���͂����ɋC�ɓ�������ł��ˁB
�����@�����A�x���A�x�������B
�|���@�Ȃ�ł��Ƃ����ƁA���܂܂ł̐��̒��́A�Ⴊ�������l�͎x������l�A�Ⴊ���������Ȃ��l�͎x����l�A�Ƃ����̂��펯�ł����B�ł��A���������n�߂悤�Ƃ��Ă��銈���́A�Ⴊ��������Ƃ��Ȃ��Ƃ��A�Ⴂ�Ƃ��N���Ƃ��W�Ȃ��A�������ł��邱�ƂŊF���x�������Ă����鐢�̒��ɂ��Ă������I�@�Ƃ������̂���������ł��B������u�v���b�v�v�Ƃ������t�́A�܂��Ɏ������̊����ɂ������Ǝv���܂����B
���ƁA�u�X�e�[�V�����v�͉w�Ƃ����Ӗ��ł����ǁA��Ԃ͉w�Ń|�C���g�̐�ւ������邶��Ȃ��ł����B�F���������̊����Ŕ��z�̐�ւ������Ăق����A���������v������u�v���b�v�[�X�e�[�V�����v�Ƃ������̂ɂ�����ł��B
�����̓���
�Ԃꂸ�ɐi�ނ���

���l�̂��o�r�זE����������Ԗ��זE�̈ڐA��p�����{����L�҉���闝���w�������̍�������v���W�F�N�g���[�_�[©����
�|���@���コ��̓A�����J�ɍs������A�ǂ̂悤�Ɋ�Ȉ�A�����҂̓������ł�������ł����B
�����@���㎵�N�A�V�������Ö@�����邼�Ǝv������ŁA�ӋC�g�X�Ɠ��{�ɖ߂��Ă��āA�Տ���Ƃ��Ċ��҂����f�Ȃ���A���s��w�ōĐ���Â̌����Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ�܂����B
�����́A�A�����J�ł̃{�X�⑽���̌����ҁA��Ȉォ����u����Ȃ��Ƃł���͂����Ȃ��v�Ƒ�����ꂽ��ł��B
�|���@��������Ȃ������ƁB
�����@����́A�����̊�Ȉ�͐_�o���זE�̐��E�g�b�v���x���̌������܂��m��Ȃ������A���ۂɊ��҂���Ɛڂ��Ȃ���b�����҂ɂ͏����̉��P�ł��ǂ�قNJ��ł��炦��̂��Ƃ������҂���̃j�[�Y��������Ȃ���������Ȃ�ł��B
������A��������Ă��������͂ɐ�������Ȃ������A��������߂Ȃ������̂́A�����̂ق����ނ�������̕����L���Ƃ����v��������������Ȃ�ł��ˁB
���ꂩ��A�������n�߂�Ǝ��肪�����Ȃ��Ƃ��������Ă��������ł����ǁA����l�́u��������v�ƌ����A�ʂ̐l�͋t�̂��Ƃ������B���ꂪ���������ɁA�u�l�̌������Ƃ������A�Ō�͎����̎v�����ʂ�ɂԂꂸ�ɍs�����Ƃ���Ԃ�v�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�������A����N�����L�����������Ă����ŁA�ł��B
�|���@�Ȃ�قǁB�����A���ۂɌ�����i�߂Ă����̂́A��������ς�������Ȃ��ł����B
�����@�����B�����́A�]���Ԗ��������_�o������ܔN���A�����ď\�N�Ŏ��Â̖ړr�������ȂƎv���Ă�����ł����ǁA�����͊ȒP����Ȃ������B����ς�]�ƖԖ��ł͊��זE�̎�ނ��Ⴂ�A�]�̊��זE�𑝂₷�̂�������Ƃ���������……�A����ł͂�������̐l�����Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ȂƁB
�|���@���̉ۑ�͂ǂ����z���Ă�������ł����B
�����@����Ȏ��ɒm�����̂��A���㔪�N�ɃA�����J�ł���ꂽ�u�d�r�זE�i���זE�j�v�̑��݂ł����B�d�r�זE�́A�̂̂�����זE�ɂȂ�閜�\�זE�ł��B
����͂��܂���Řb�������Ƃ͂Ȃ���ł����A���̍��A�Ԗ��̍Đ���Âɍ����Ŏ��g��ł��錤���҂���������������Ȃ������Ƃ̂��ƂŁA�����Ȋw�Ȃ̐������̕�����ˑR�d�b���|�����Ă�����ł���B�u�Ԗ��̍Đ���Â̌�����A�ܐ疜�~�ő���܂����H�v�ƁB
���͓����A�S�\���~�قǂ̌�����Ō��������Ă����̂ŁA�u���̓d�b�͍��\��������Ȃ��v�ƁA�{���ɕ|���v�������܂����i�j�B
�|���@���\���Ǝv�����i�j�B
�����@�ł����̕����u�_�o���זE�ł͓���B���ꂩ��͂d�r�זE���v�ƌ����Ă�������A���ȏȂ���������̎�����T�|�[�g�����Ă���������悤�ɂȂ�܂����B
�������Č������i��ŁA��Z�Z�l�N�A�T���̂d�r�זE�ŖԖ��̍Đ����ł��邱�Ƃ�_���Ŕ��\������ł��B����́u�쒷�ނ̂d�r�זE�����ÂɎg����v���Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ď������_���ɂȂ�܂����B
���n���~����
���o�r�זE�̓o��
�|���@�d�r�זE�̎��Âł͓��{�����E�����[�h���Ă�����ł��ˁB
�����@�����A�l�Ԃ̂d�r�זE���g���������́A�K�C�h���C�����Ȃ��A���{�ł͂܂��F�߂��Ȃ�������ł��ˁB�d�r�זE�͑��l�̍זE�ŋ��┽��������܂����A����҂�Ɖu�}���܂̊댯�ɚA�i����j�����Ƃ͂������Ȃ������̂ŁA�����S�O�i���イ����j���Ă��܂����B
����������A��Z�Z�ܔN�����������ȁA�A�����J�̃x���`���[��Ƃ��q�g�̂d�r�זE�Ŏ���������Ƃ����\������Ă�����ł��B
�m���Ɂu���{�̓}�E�X�i�����j�������̂͂��܂������ˁv���ē�������悭�����Ă��܂����B�����Ń}�E�X���������Ƃ͂ł������ǁA�̐S�̐l�Ԃ̎��Â̓A�����J�ȂǂɑS�������Ă�����Ă��܂��B�ڂ̍Đ���Â������Ȃ邩�Ǝv���ƁA�����������������ł��ˁB
�|���@����z����Ă��܂��ƁB
�����@�Ƃ��낪�A���̉������Ďc�O���Ǝv���Ă������ɁA�o�Ă����̂����o�r�זE��������ł���B
�|���@�����A�R���L��i�����j�搶�́B
�����@�_�����o��O���畷���Ă͂�����ł����A���o�r�זE�͋��┽���̖�肪�Ȃ��A�ϗ��I�Ȗ����N���A�ł���Ƃ������ƂŁA����͂����т����肵�܂����ˁB
���͓����̎��Âɐ������A�l�Ԃ̎��Â��ł����O�܂ŗ��Ă��܂�������A����͐�Ύ����Ŏ��Ö@��������ĐS�Ɍ��߂܂����B�R���搶�ɂ��i���X�Řb���Ă��������āA�u�ܔN�Ŏ������܂��v�Ǝv����`������ł��B�ォ�畷���ƁA���̎��͖{�C�ŐM���Ă���Ă��Ȃ������悤�ł����i�j�B
����ł��o�r�זE���g�������ÂɎ��g�ݎn�߁A��Z��l�N�A������ϐ��̊��҂���ɂ��o�r�זE���番�������זE���ڐA�����p�𐢊E�ŏ��߂Đ��������邱�Ƃ��ł�����ł��ˁB�Đ���Âɏo�����Ă����\�N�߂��|�������ƂɂȂ�܂��B
�|���@�悭���߂��Ƀ`�������W�������܂����ˁB
�����@����ς�A�ڂ̑O�̊��҂���̑��݂��傫�������ł��ˁB
���͔C���̖�肪�����āA��Z�Z�Z�N�ɋ��s��w���痝���w�������Ɉڂ��Ă����ł����A���ʂȂ��Ȉ�͂����Ō����𑱂���̂���߂āA�a�@�ɋ߂��ł��B�����Y��ł����ǁA����܂Ŋ�Ȉ�Ƃ��Đڂ������҂���⊳�҉�̕��X�Ɂu�V�������Ö@������܂��v���Đ錾���Ă��܂�������A���̖͏d�����A��Ύ��Ȃ�����ȂƁA�����𑱂��铹��I�Ƃ����o�܂�����܂��B
�|���@���҂���Ƃ̖������ւ̃��`�x�[�V�����ɂȂ����B
�����@�܂��A�O���Ŗ��T���҂��f�@�ɗ��āA�u�V�������Â͂ǂ��Ȃ�܂����H�v���ĕ�����Ă���
��������A�u���͌�����߂܂����v�Ƃ͌����܂���ł�����ˁB
�S�̐S����
�x������
�����@�v���b�v�E�X�e�[�V�����̊������A�O���ɏ悹��̂͂ƂĂ���ς�������Ȃ��ł����B
�|���@�v���b�v�E�X�e�[�V�����𗧂��グ�āA�ŏ��͑S���̃`�������W�h�ɃA���P�[�g����邱�Ƃ���n�߂܂����B����������A�����̐l���u���������v�u�p�\�R��������Ύd�����ł���v�Ɠ������̂ŁA���N�ɏA�J��ړI�ɂ����p�\�R���Z�~�i�[���J�Â�����ł��ˁB���̃Z�~�i�[�ŋZ�p���K�����`�������W�h�Ƀv���b�v�E�X�e�[�V��������Ƃ��琿���������d��������U���Ă����B���������r�W�l�X���f���������Ă����܂����B
�����A�����̓p�\�R���̒l�i�����ɍ����A�R���s���[�^�Ŏd��������ƌ����Ȃ���A�c�̂ł͈��������Ă��Ȃ�������ł��B
�����@�����ōw���ł��Ȃ������B
�|���@�����玄�́A�Ȃ����̂͂r�n�r���o���āA�����Ă����l�̋��͂ő����悤�ƁA�x���҂̃l�b�g���[�N�Â���Ɏ��g��ł����܂����B�K���A���͎��肩��u�S�̐S���ɑۂ��d�ɐ����Ă���v�ƌ�����قǁA�ǂ�Ȑl�̑O�ɏo�Ă��|���Ȃ������̂ŁA�тт炸�Ɍo�c�҂̕��X�ɉ�ɍs���āA�Љ�v���Ȃǂ̖ʂ���d����������ʂ�i���A��s�������Ă��������I�v�ƁA��t�����Ă�������ł��ˁB
�����@�����A��s�������ƁB
�|���@�����������g�݂𑱂��Ă������ƂŁA�A�b�v���Ђ���p�\�R������t���Ă��炤�ȂǁA����Ɗ����̊�Ղ��ł��Ă����܂����B���ꂩ��A�V���Ƀv���b�v��X�e�[�V�����̊������Љ�ꂽ�̂����Ă����������}�C�N���\�t�g���В��̐������i�Ȃ邯�܂��Ɓj����ɂ��A�uWindows95�v�����Z�b�g�������Ă��������܂����B
���т���ɂ́A���̌�������g�̕����A�n�Ǝ҂̃r���E�Q�C�c��ɂ��Љ�Ă��������Ȃnj𗬂������A��Ƀv���b�v��X�e�[�V�������Љ���@�l������ۂɂ��ꉭ�~�̊���̂��x�������������܂����B
�悤�₭���オ
�ǂ�����

���N46�ɂȂ鈤���̖��I����Ƃ̈ꖇ

�v���b�v��X�e�[�V�����̃X�^�b�t�����ƁB�v���b�v��X�e�[�V�����Ŋw�����̃`�������W�h�������ݑ�Ő��������Ɠ����Ă���
�|���@�����A����ς莄�����̑��̍��̊����ł͌��E�������āA�Ⴊ���Ҍٗp�̖@���ȂǁA���̕��j���ς��Ȃ��Ƃ��߂��ƒi�X�C�Â��n�߂���ł��B�Ⴆ�A��Ƃ⊯���Ɉ�芄���̌ٗp���`���Â���@��ٗp��������܂����A����ł͎���ł̉�삪����I�ɕK�v
�ŁA�ʋł��Ȃ��`�������W�h�͎x�������܂���B
�����@����ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƁB
�|���@����œ����́A���������̎咣��ʂ����߂ɁA�c�̌��̂悤�Ȍ`�ŗ͂����ō��̕���������@������݂����ȉ^���A���@����������ł����ǁA���͂�����A����@��������������炱�����茮���J���Ă���鋦�͎҂����Ɉ�l�A��l����ق��������Ⴄ���Ȃ��Ǝv������ł��B
�����āA���ۂɎ��͂̐l�ɂ��낢�둊�k���āA�����A�J���ȁi���E�����J���ȁj�̏Ⴊ���Ҍٗp��ے������������̕��ɁA�u���Ȃ����j�Љ�Ŋ撣���Ă��邩�Ǝv���܂��B�������������c�̂������āA�`�������W�h�̐l�����Ƃ���Ȃ��ƂɎ��g��ł��܂��B��x����Ă��������܂��v�Ƃ����M���莆�������܂����B
�����@����͂܂��������B
�|���@���̏����ے��́A�Ⴊ���Ҍٗp�Ɋւ��鐭����ǂ�ǂ�i�߂Ă��āA���Ԃł��L���ȕ��ł�������A��͖̂�����Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���炭���āu������܂��v�ƕԎ����͂��āA�����̉����ւ܂ʼn�ɍs������A�u�ł���͈͂ʼn��������v���Č����Ă�����������ł��B
�����@�i�~�˂��̔M���v�����`�������ł��ˁB
�|���@���ꂩ��A�����ւŕ�������Ă��ꂽ��A���낢��ƉA�Ȃ���x���Ă��������Ă�����ł����A���㔪�N�A���傤�ǃv���b�v�E�X�e�[�V�������Љ���@�l���������A�u�M�����镔�����ے��ɂȂ�������v�ƁA�Љ�Ă����������̂����،��q����ł����B
�����@�����A���J�ȂŎ��������߂��B
�|���@��������������Ƀv���b�v�E�X�e�[�V�����̎��g�݂��������{�������Ă����A�Ɏf���܂����B����������A�Z��������ӂœǂ�ł�������A�u����Ŏ�����i�Ɠ������B�Ȃ��Ȃ珗���������ɂ����Ƃ������ƂƁA�Ⴊ���҂������ɂ����Ƃ������Ƃ͓����B�ꏏ�ɓ��{��ς��܂��傤�v�ƁB
�����@�S�������ł��ˁB
�|���@����Ō��q������u�Ⴊ���҂��ݑ�ł�������悤�Ɂv�Ƃ����e�[�}�̈ψ���𗧂��グ�Ă��������܂����B
�܂���Z�Z���N����͓�l�Łu���j�o�[�T���Љ��n�����鎖�������v���W�F�N�g�v���J�n���A�\�Ȃ̎����̎Q��āA�������\��N�ԕ���𑱂��Ă��܂��B
���͎��A�����Ȃ̐R�c��ψ����\���N�Ԗ��߂Ă��₯�ǁA�̂͋c��ɂ����Ȃ������u�Ⴊ���҂̏A�J�v�����X�Ɏ��グ����悤�ɂȂ�A��Z�ꔪ�N�ɁA���߂āu���c�v�Ɂu�Ⴊ���҂��Љ�̎x����Ɂv�ƋL�q����܂����B
���ܐ��{���i�߂Ă���u�ꉭ������Љ�v�u���������v�̍l�����v�Ɂu�Ⴊ���̂���l���ݑ�ł�������悤�ɂ��悤�v�Ƃ����ꕶ������A������āA�v���b�v�E�X�e�[�V�����̒n�����Ɍ��E�_�ˎs�ł́A�`�������W�h�̍ݑ�[�N�𐄐i����v���W�F�N�g��\�Z�����A�����o���܂����B
�����@���オ����ƒǂ������B
�|���@����́A�����x���Ŏ��������̊����A�i�����F�m���ꂽ�ƁA�����������������ł��ˁB���ہA����܂Ńv���b�v�E�X�e�[�V�����̃R�[�f�B�l�C�g�ŌܕS�l�ȏ�̃`�������W�h���ݑ�ŏA�J���A���ܔނ�̓f�U�C����V�X�e���J���ȂǂŊ��Ă���Ă��܂��B
�V�������z������ɂ�
�����O���[�ŏW�߂�
�|���@���コ��́A�ڂ̎��Â̐V�������E���Ă����킯�ł����A���̔��z�͈͂�̂ǂ����痈����̂Ȃ́H
�����@��͏��Ɏ����Ŕ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B
�����̐l���A���̐l�͂悢�l�����l�A����͐������������Ȃ��Ƃ��A�ŏ����畨���ɔ��������Ĕ��f���Ă��܂������Ȃ�ł����A���ꂾ�Ə�S���킬���Ƃ���āA�厖�Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ă��܂��\���������ł��ˁB�Ⴊ���҂������ŁA�����̐l���ŏ�����Ⴊ��������l�A�Ⴊ�����Ȃ��l�ƕ����Ă��܂�����A�厖�Ȃ��Ƃ��S���킬������Ă��܂��B
�|���@�܂��ɂ����ł��ˁB
�����@������A���͂悭���{�Łu���̓O���[�ŏW�߂Ȃ����v�ƌ����Ă����ł��B���̘_���̂��̃f�[�^�͉����������A����͉����������Ȃ��Ƃ��������ŏ����W�߂Ă����ƁA����ɃO���[�̔Z�W���d�Ȃ��Ă����āA���鎞�A����͐������Ǝv����A���������Ă���Ƃ��낪�т�[���ƌ����Ă���u�Ԃ������ł���B
����ς�A�Ȋw�҂̐_���͏��߂��甒�������ɋ^�����Ƃł����āA�ł��^���ׂ��͎������g�̍l���Ȃ�ł��ˁB���̍l���A�����͐��������ǂ�����������p�x����ᔻ���Ă݂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�|���@����͐��コ��̌����҂Ƃ��ẴZ���X��ˁB�Z���X�̈����l�́A�Ȃ��Ȃ����ꂪ�ł��Ȃ��B
�����@���ƁA�w���ɂ́u���̈悪�����Ƃ�����v�Ƃ����A�h�o�C�X���Ă��܂��B�Ⴄ���̂�g�ݍ��킹��ƁA�K���V�������̂����܂���ł���B���̏ꍇ�ł��A�]�̊�b���������錤�����ɐ��̈Ⴄ��Ȉオ����������V�������z�����܂ꂽ�B�b��ɂȂ����s�R���Y����́u�o�o�`�o�v�ƈꏏ���Ǝv���܂��B�y���ƃA�b�v�������������ł��i�j�B
�|���@���͂����l�Ɛl�A�l�Ԃł�肽���̂�B���͎����̂��Ƃ��u�l�Ɛl�Ƃ��q�������P�����v�u�|��}�V�[���v���Č����Ă�����ǁA�l�Ɛl�Ƃ��q���邱�ƂňႤ���́A�V�������̂����܂�Ă���A���ꂪ�������D���Ȃ��B
�����@�l�Ɛl���q���������A�ł��傫�ȉ\�������܂�܂���ˁB
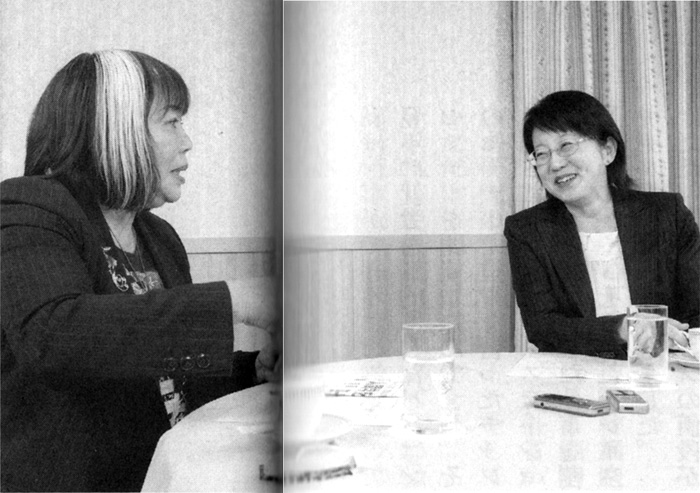
�|����s�\�ɒ��킵�Ă������Ƃɂ�������W�̎킪����܂��
������V�������Ƃɒ��킵�Ă������Ƃ��y�����Ďd��������܂���
�|���@�`�������W�h�Ƃ������t��ł��A�`�������W�h���g���������A�e���Ƃ̐l�A�����Ƃ��������A���ꂼ��Ӗ��������ɈႢ�܂��B�ł��A�l�͈Ӗ����H��������܂܉�b���Ă��邱�Ƃ������B
����������ɖ|�A�l�Ɛl�Ƃ��q���āA���悢���́A�V�������̂�ł������B���̗͂͂��ꂩ��������Ă��������ł��ˁB
�����玄�́A�{���A���[�_�[�^�C�v�ł͂Ȃ��āA�O�ꂵ���R�[�f�B�l�[�^�[�^�C�v�Ȃ�ł���B
�����@����A�i�~�˂��̓��[�_�[�^�C�v�Ɍ����܂����ǁi�j�B
�|���@�܂��A���͕��C�~���L���܂��邩��A���������邾���i�j�B
���{�͐��������Ƃ���
���ɂȂ��`�����X�ɂ���
�|���@���A������������������番�����₯�ǁA�̂͂����烏������Ă��܂����ɖ߂��A�����ɖ߂��`�����X��������ł���������ł��B�ł��A���܂͈�x���݊O������A�����߂�`�����X���Ȃ��悤�ȋC������̂�ˁB
�����@�m���ɂ����ł���ˁB
�|���@���̂Ƃ���ɑ��k�ɗ�����l�͑f���Ȃ����l�������āA���̒��ɍ��킹���Ȃ��A�͂ݏo���Ă��܂���������������Ȃ����Ǝ�����ӂ߂Ă����ł��B����́A���܂̐��̒��ɂ͂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������������āA�����̐l�����̓���K�������Ȃ�����߂��Ǝv������ł��邩�炾�Ǝv����ł��ˁB
�����A�N�����̓��𐳂����ƌ��߂��̂��Ęb�ł���B���������^������ĂȂ����ɐl�͐��_�I�Ɏ���Ă��܂��B������A���͂����Ď��������݊O�����ƂŁA�u�ꉭ���s�lj��v��_���Ă��������Ɓi�j�B
�����@�ꉭ���s�lj��i�j�B
�|���@����ς�A�����Ȑl�������������āA�������������Đ����Ă�����Љ�ɂ��Ă����ɂ́A���ɂ͊F���������Ƃ������Ƃ��^���A�����O��邱�Ƃ�|�����Ă͂����Ȃ��B�����łȂ���A�{���̈Ӗ��ł́u�C�C�����i�������ǂ��j�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ���Ȃ����ƁB
�����@�i�~�˂��͂܂��ɂ��̑��݂��̂��̂��C�C�����ł���ˁi�j�B
����ŁA�����i�~�˂��ƍl�����͈ꏏ�Ȃ�ł����ǁA���ܗ����w�������ŕS�N��̖������l����v���W�F�N�g���ł��Ă��āA�Ⴆ�A�S�N��̈�Â͂ǂ��Ȃ��Ă��邩���l���Ă����ł��ˁB
�|���@�S�N��A�ł����B
�����@�����A�S�N��̓��{�͂��܈ȏ�̒�����Љ�ɂȂ��Ă��܂�����A�ڂ������Ȃ��A�����������Ȃ��ȂǁA�̂̒��q���悭�Ȃ��l��������O�ɂȂ�ƁB�����Ȃ�ƁA���N�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Œ�ϔO��A�N���Ⴊ���҂ł�������Ȃ����Ƃ����Ⴂ������F������������܂�����A�����Ȑl�������炵����������A�{���ɃC���N���[�V�u�i��I�j�ȎЉ�ɂȂ�\��������܂��B�����ɂ���ẮA������Љ�̓��{�͐^�̃C���N���[�V�u�ȎЉ�ɂȂ�`�����X���Ƃ��������ł��B
���邢�́A�Đ���Â̐i���ɂ���āA���߂Ɏ��ւ���Ƃ��������a�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�Ƃ��������Ɍ������Ă�����������܂���B
�|���@���������B���{�͂��ꂩ��`�����X�Ȃ�ł���ˁB�l�ނ͕s�\�ɒ��킵�āA����������A�������Ă������ƂŔ��W���Ă����Ǝv����₯�ǁA����ɂ������W�̎킪����Ɍ��܂��Ă����ł���B�Ȃ�ŊF�A������l�K�e�B�u�Ɍ���̂��s�v�c�ł��傤���Ȃ��B
���������������̊����Ɏ��g��ł��������͂̈�ɂ́A��e�Ƃ��āA�u�������̂܂c���Ď��Ȃ�ւ�I�v�Ƃ����v��������܂��B
���������܂ŁA���̖��I�͍��N�l�\�Z�ɂȂ��ł����A���܂������u���ꂿ���v�Ɨ����ł��Ȃ����A�x�C�r�C�^�C�v�Ȃ̂ŁA�����邱�Ƃ��ׂĂ�N���Ɏx���Ă����Ȃ��Ɛ������܂���B���̎x���Ă���킴��Ȃ��l���ǂꂾ������Ă�����Љ�ɂł��邩�B����͎��Ɏc���ꂽ���ɂ̉ۑ�ł���A�u������i�~�˂��̍ő�̉�ԁv�ł�����̂ŁA���ꂩ������̉����̂��߂ɂł������̂��ƂɎ��g��ł��������ł��ˁB
�����@���͂��܍Đ���ÂɌ��炸�A���҂���̐������悭����A�l���K���ɂ��Ă������߂ɁA�V�������Ƃɒ��킵�Ă����̂��y�����Ďd�����Ȃ���ł��ˁB���̐��������Ƃ����v���������āA���ꂩ��������ɗ^����ꂽ�g���ɑS�͂�s�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B