神戸市で実証実験が進められている「自律移動支援プロジェクト」。音声で位置情報や誘導案内も提供される次世代のシステムとして早くから注目されているが、そのモニター体験会が12月まで行われる。先月24日から始まった第1期、視覚障害者対象のモニター実験の様子を見てきた。
点字ブロックにICタグ 携帯端末から位置情報
いつでも、どこでも、だれでも

街路でのモニター実験
同プロジェクトは、国土交通省が主導する産官学共同の事業として昨年度から始まった。時や場所を問わずインターネットなどの情報ネットワークに接続できる「ユビキタス」の技術を利用して場所情報を提供するシステムで、「いつでも、どこでも、だれでも」移動経路や目的地、交通手段などの情報を入手できる環境づくりを目指している。
「ユビキタス」は「いたるところにある(偏在する)」という意味のラテン語に由来する言葉で、今回のシステムでも道路や建物、公園など、街中のさまざまな場所にICタグや、無線でデータを一定範囲に送る通信機器が取り付けられるのが特徴だ。ICタグなどにはそれぞれ、固有の位置コードが与えられ、専用の端末がそれを読み取り、ネットワークに接続することで、その場所の情報が提供されるという仕掛け。市街地の随所にある住居表示板や道路標識などにICタグが広がれば、視覚障害者が位置情報を入手する有力な手段になりうる。
8月24日から神戸市の中心街・三宮で始まった視覚障害者向けのモニター実験は、神戸市役所周辺の道路エリアと、神戸港中突堤の旅客船ターミナルの2ヵ所で行われた。いずれもICタグの埋め込まれた点字ブロックの上を専用の白杖(はくじょう)で歩き、杖先(つえさき)がICタグと接触すると、音声が聞こえるシステムの体験で、音声案内の内容や表現方法、音声の提供場所について利用者の意見集約が狙いとされた。
参加者が装着した装備は、首からぶら下げた携帯端末、携帯端末と接続した骨伝導式のヘッドホン、そしてベルトに装着する、ポケットベルサイズの方位センサー。この方位センサーを着けることで、このシステムが位置情報の提供だけでなく、誘導にも使えるようになる。
例えば、神戸市役所前の歩道での実験。北向きに線状の点字ブロックを歩いていると、「ピッピッ」と合図があった後、「5メートル先、二またの分岐です」と合成音声の案内が聞こえ、点状ブロックのその地点にたどり着くと、「二またの分岐です。直進はセンター街、三ノ宮駅方面。右はサンチカ方面下り階段入口です」と聞こえてきた。階段に向かうと、「1段上がると、踊り場。そこから下り階段です。全部で39段。踊り場は1ヵ所。踊り場までは19段です」と詳しい情報も。同じルートを戻り、再び「二またの分岐」にたどり着くと、今度は「正面は市役所。右はセンター街、三ノ宮駅方面。左は東遊園地、神戸港方面」と、利用者の向きに応じた情報が提供される。右に進むと、「左は神戸花時計です」と、有名な観光モニュメントの案内も聞こえてきた。
「ユビキタス」技術を利用
「歩行に自信が持てる」
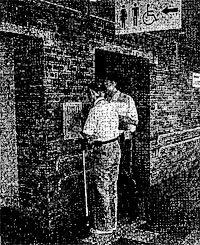
施設内での設備案内
附属盲高等部普通科2年の梅村光さん(全盲)は神戸出身で、帰省中に実験に参加した。「良かったです。全国にあれば、自分の行動範囲が広がると思います」と感想を語った梅村さんは普段、寄宿舎から外出することが少ないという。仮に学校の近くにこのシステムがあれば、「自信を持って歩けるように日常的に使いたい」と話していた。
40代の男性参加者も「実験段階としては良いシステム」と感想を述べ、今後も実験に協力すると前向きだった。同時に「携帯端末が高いものになっては困る」「歩き慣れていない視覚障害者のデータも交えて検証してほしい」など、率直な意見を関係者にぶつけていた。
官と民の連携がカギ
神戸市は来年2月開港予定の神戸空港に、このシステムを導入する計画だ。今後、同じように公共施設で統一的に導入するルールが確立されれば、情報インフラとして視覚障害者にも期待できそうだ。一方で、街中の誘導案内として普及させるには課題が残るだろう。ピンポイントでなく、面として情報が提供される地域がどこまで広がるかが鍵になるが、官だけにきめ細かな情報提供を期待するのは難しく、地元のNPOなどと結びつくことも必要になるだろう。視覚障害者も、このシステムをどんな場面で使いたいのか、実験段階から率直に話すことも大切だと感じた。
(濱井良文)
