|
|
「e-FORUM2004〜ITによる障害者の在宅ワークを実践して」というイベントが、去る3月1日と2日、三重県津市で開催された。ITを活用したチャレンジドの在宅ワークを推進する三重県の産学官民連携プロジェクト「eふぉーらむ」が、その中間報告として催したもの。これまでの活動を報告するとともに、チャレンジドIT支援の先駆者たちを招いて、今後の課題が議論された。
(構成・写真:中和正彦=ジャーナリスト)
|
1日数時間でも
働けるチャンスを
|
|
「障害があってもなくても、働く意欲と能力がある人が働けるようにするのは、当然のことだと思います」
「eふぉーらむ」プロジェクトマネージャーの村田幸子さん(元NHK解説委員)は、オープニングでそう切り出した。
eふぉーらむは、まさにそのために一昨年8月に設立された。県が旗振り役になってNPO・企業・行政・個人などの会員を募り、ITで仕事のできるチャレンジドを育成しながら、仕事を受注してチャレンジド在宅ワーカーに提供する。
在宅ワークの運用は、まずeふぉーらむのスタッフが営業して仕事を受注する。受ける仕事は、Webサイトの制作・管理、データベース構築、データ入力・集計など。仕事が取れたら、メーリングリスト(ML)に登録の在宅ワーカー全員に、仕事の内容、納期、求められるスキルなどの情報を流し、希望者を募る。基本的には先着順に採用し、その仕事を受けたメンバー専用のMLで仕事を進める。
通勤フルタイム労働なら1人分の仕事も、必ず複数名のチームで進める。そうすることによって、障害のために1日数時間しか働けない人も参加可能にし、なおかつ意思の疎通や役割意識と責任感など、ヒューマンスキルを磨くことも狙う。
プロジェクトリーダー(PL)の岡本悟さん(三重県地域振興部)が行った活動報告によれば、実際に仕事の受注を開始した2003年1月から今年2月末現在までの1年2ヵ月に、34件・約1,900万円の仕事を受注し、そのために延べ118名の在宅ワーカーが働いたという。
当日はそのうちの4名の在宅ワーカーと、在宅就労を目指してeふぉーらむでパソコン勉強中の1名が登場した。
|
eふぉーらむが
私の生活を変えた
|
|
山本並美さんは、幼い頃に事故で片足を失って義足装着の身。大卒後、通勤の仕事に就いたが、体が続かず2年で退職したという。しかし、その後、結婚・出産を経て、昼間は作業所のマネジャーとして働き、夜は子どもを寝かしつけからeふぉーらむの在宅ワークという働き者。この春には、地元に新しい作業所が開設の予定で、「eふぉーらむとこれまでの作業所で得た知識を生かし、相互に役立てていきたい」と抱負を語った。
脳性まひの障害を持つ中山秀子さんは、20年も前から弟が使うパソコンに興味を持っていたが、ずっと「マウス操作は私には無理」と諦めていた。数年前、愛用のワープロ専用機が壊れ、周囲の勧めに押されて、ようやくパソコンを購入。そこから、Windowsの「ユーザー補助」にマウス操作をキーボードに置き換える機能があることを知り、eふぉーらむに出会い、在宅ワークへと急展開。「つい数年前まで私にとってただの箱だったパソコンが、今では生活になくてはならないものになるなんて、自分でも想像しませんでした」と喜ぶ。
同じ脳性まひの障害を持つ渡辺隆典さんも長い間、ワープロ専用機止まりだったが、eふぉーらむと出会ってパソコンに挑戦。在宅就労を目指している。「最初は電話で質問していましたが、今はメールで聞けるようになりました」という。
|
ベンチャー・チャレンジド
ユーザー本位を学ぶ
|
|
一方、事故で車いす生活になった羽生浩史さんは、1991年にワープロ検定に挑戦して以来、ITに自分の可能性をかけ、98年に企業就職。2000年にはインターネット関連事業で独立。これまで100以上のWebサイトを制作し、最近はeラーニングのシステム開発も手がける。そんな最先端を行く羽生さんも、eふぉーらむには学ぶことが多いと言う。
「これまで、見栄え重視のサイトを作ってきました。クライアントが喜んでくれたので、それで自分も満足していました。eふぉーらむの仕事で初めてユーザー本位の作り方に気づかされ、自分の慢心を思い知らされました。ユーザビリティやアクセシビリティについて、ここでもっと勉強していきたい」
養護学校を卒業してまだ1年ながら、Webサイトのデザインなどで活躍し始めている伊藤智之さんは、「いまの私は自信を持って言えます。どんな障害があろうと、生きがいを見つけて仕事をすることができます。夢を諦めないでほしい。障害があるから健常者より努力が劣るとは考えないでほしい」。
5人の中で最も若いが、障害は最も重く、そのために声はか細い。だが、その言葉は、声に耳を傾けて静まりかえった聴衆の心に深く響いたはずだ。
|

「eふぉーらむ」プロジェクトマネージャーの村田幸子さん |
|

プロジェクトリーダーの岡本悟さん(三重県地域振興部) |

ユーディットの代表取締役の関根千佳さん |

社会福祉法人・東京コロニーの堀込真理子さん |

パソコンボランティアのNPO法人「練馬ばそぼらん」を率いる関和子さん |
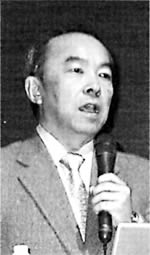
星城大学リハビリテーション学部の畠山卓朗・教授 |
|

講演する竹中ナミねぇ |
|
チャレンジド就労支援は
福祉サービスではない
|
|
5人の発表は、「この機会に」と初挑戦した人も含めて全員がパワーポイントを使い、きちんと持ち時間に合わせて話をまとめた見事なものだった。仕事でも機会があれば自分から手を挙げ、きちんと品質と納期を守って仕上げているであろうことが想像された。
だが、在宅ワーク登録者すべてが彼らのようなわけではない。PL・岡本さんはこんな事情を明かした。
「いま64名の登録がありますが、これまでの仕事に一度でも関わったのは40名弱です。仕事の情報を流しても手を挙げない人には『失敗してもいいから一度関わってみてください』と声を掛け、時には『何のために登録したんですか』と厳しく問うのですが……」
ここには、しばしば指摘される障害を持つ本人にありがちな課題が感じられる。すなわち、自発的な行動による成功体験が乏しいことから来る「自信のなさ」。自分でする前に周りがしてくれることに慣れた結果の「待ちの姿勢」。障害を理由に過度な要求をしても応えてもらったことに由来する「甘え」などだ。
こうした課題を持った人がeふぉーらむのような活動に触れれば、次のように誤解することが容易に想像される。すなわち、「登録しておけば障害に応じて仕事をもらえるのではないか。行政がやる事業なら、そうしてくれて当然だ」。
その誤解を避ける意味もあってか、eふぉーらむは活動の使命を「仕事の提供」ではなく、「機会と情報の提供」としている。提供された機会と情報を自分のものにできるかどうかは、常日頃から自分の力を磨いているかどうかによるのだ。
|
チャレンジドIT支援
先駆者たち大いに語る
|
|
働こうとするチャレンジドと向き合ってきた講師・パネリストからは、彼らの内にありながら課題の克服するを期待する、厳しくも温かい言葉が聞かれた。
「情報のユニバーサルデザイン」の第一人者で、障害を持つ社員・契約社員を活用する経営者でもある(株)ユーディット代表取締役の関根千佳さんは、「障害のためにできないことがあるのはわかります。しかし、仕事で大事なのは問題解決能力です。どうすればできるか。独りではできなくても、誰かと組めばできるはず。それを自分の頭で考えるようになってほしい」。
重度身障者へのIT講習と就労支援で数々の実績を上げてきた社会福祉法人・東京コロニーの堀込真理子さんは、「私たち支援者よりも先に、本人たちが声をあげるようになってほしい。なぜ働きたいのか。そのために何が必要で、現状どうなっているのをどう変えてほしいのか。自分で調べて訴えて、道を切り開いていく気持ちを持ってほしい」。
しかし、もちろん課題はチャレンジドの内だけにあるのではない。パソコンボランティアのNPO法人「練馬ばそぼらん」を率いる関和子さんは、r width="100%" size="3" color="999900">
|

