教育ながさき 2008年11月1日発行より転載
障害者からチャレンジドへ
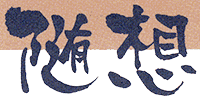
障害者からチャレンジドへ
社会福祉法人 プロップ・ステーション
理事長 竹中 ナミ

1948年兵庫県神戸市生まれ。神戸市立本山中学校卒。
重症心身障害の長女を授かったことから、独学で障害児医療・福祉・教育を学ぶ。1991年、草の根のグループとして社会福祉法人プロップ・ステーションを発足。98年、日本で唯一のICTを使ったチャレンジド(障害がある人の可能性に着目した、アメリカで生まれた新しい言葉)の自立支援組織として厚生大臣認可の社会福祉法人格を取得し、理事長となる。「チャレンジドを納税者にできる日本」をスローガンに、95年より毎年チャレンジド・ジャパン・フォーラム(CJF)国際会議を主宰。
社会保障国民会議委員、財務省財政制度審議会委員、総務省情報通信審議会委員、内閣府中央障害者施策推進協議会委員、国土交通省「自律移動支援プロジェクト」スーパーバイザー、などを歴任。著書「プロップ・ステーションの挑戦」(筑摩書房)、「ラッキーウーマン〜マイナスこそプラスの種」(飛鳥新社)。ニックネーム「ナミねぇ」で親しまれている超元気な関西人。
今回は、ICTを駆使してチャレンジド(障害者)の自立と社会参画、とくに就労の促進を目標に活動されているナミねぇこと竹中ナミさんにお話をうかがいました。
− プロップ・ステーションを立ち上げた目的をお聞かせください。
私の娘が重症の心身障害者で、現在35歳になっていますが、彼女はまだ私のことをお母さんと認識していません。そういう娘を授かり、「将来的に自分が安心して死ねるかどうか。」と考えたときに、今の日本の状況を見ているとなかなか大変なことが多いなということに気が付きました。とりわけその中でも「障害者=可哀(わい)想な人」で、福祉の対象で、社会がその人たちに期待していません。可哀想というのはある意味で期待していないのと一緒なわけです。だけど本当にそうかなと思いまして。娘を通して出会ったチャレンジドの方々とお付き合いしてみると決して、「可哀想」とか、「〜ができない」という言葉でくくれるのではなく、いろんなことができるけど、それが発揮できない、もしくは発揮することが無理だったり、発揮させてもらえなかったりしているのだと感じました。つまりそれは、逆に言うと社会から期待されていないということとイコールなんです。
その構造を自分自身で何か変えていきたいなと思いました。それは、自分の娘のためにもそうだし、たくさんの人が生き生きと仕事をし、社会を支えられる人になってもらいたい。私自身が安心して死ねるということも含めてですが、そうしたことをやりたいなと思っているときに同じ様な考えの仲間たちが集まり、始めたわけです。
だけど働くことが無理だと言われている様な人たちが「何か自分のできることを発信しよう。」と思ったら、当然、そのための道具がいるわけです。それが「これからはコンピュータじゃないか。」と重度の障害がある人たちが言いました。「そんなふうにみんなが言うんだったら、コンピュータを使ってやってみようか。」ということになり、プロップ・ステーションはチャレンジドもコンピュータの様な道具を使って、自分のできることを世の中に発信するという目的で発足したんです。
− 「チャレンジドを納税者にできる日本」に込められた思いについてお聞かせください。
「チャレンジド」というのは、障害のある人を表すアメリカの言葉です。この言葉は「挑戦する使命や課題、あるいは、チャンスを与えられた人」という考え方に基づいていて、障害があっても決してマイナスとするのではなく、「そのことによって初めてほかの人が得られなかったものが得られたり、それをもとにして新しい視点で社会が見られたりというポジティブなイメージにしていきましょう。」という考え方で、私たちも使わせてもらっています。
そして「納税者に」というのは、私が言い出しっぺではなく、ジョン・F・ケネディがアメリカ大統領になったとき、議会に提出した教書の中で、「私はすべての障害者を納税者にしたい。」と書いているんです。彼の妹、ローズマリーさんは重度の知的障害があり、そんな中で、「障害があるから働けなくて当然です。納税者になれなくて当たり前です。」という考え方こそ差別だということに気付いたわけです。だから「障害がある人を納税者にできるようにする。アメリカをそういう国家にする。」という発想は、彼としては自然だったわけです。
それが分かったときに、私は目から鱗(うろこ)が落ちました。「働けない。社会を支える人にはなれない。」と決めつけるところから日本の福祉は始まっていたのです。可哀想っていうのは対等になれないということとイコールなんです。そこに原因があったことに気付き、共感した私もこの言葉をスローガンにしてみようと思ったわけです。
だけどそれは、「障害者も働いて税金払えよ。」ではなくて、社会みんなで、その人が自分の持てる力を磨いて発揮できるようにし、納税者になれるようにする。そんな仕組みのある日本にしたいという思いから「チャレンジドを納税者にできる日本」というスローガンが生まれたんです。
ですから私たちは、ユニバーサル社会をつくろうと言ってますけど、「すべての人が自分の個性や能力を生かして、その生かしたもので、みんなで支え合いをする。」という考え方の社会を、ユニバーサル社会と呼んでいます。「チャレンジドだけでなく、女性や高齢者であれ、いろんな国籍の人であれ、みんなが何らかの形で社会を支えていける一人になろうよ。そして、無理なところは支え合ったらいいじゃない。」という温かさと同時に日本をチャンスのある国にしていきたいということなんです。
− 日本の福祉はまだ、可哀想という発想が残っているのが現状ですか?
そうですね。日本人って人情がある優しい国民性を持っていると思うんです。だから「困っている人がいたら助けてあげよう。」とか「自分ができることをこの人ができなかったら手助けしてあげよう。」という気持ちを持っています。そういう意味では、私はその気持ちはすごく大事だし、絶対失わない方がいいと思っているんです。
ただ、相手を見るときに自分よりできないところとか、無理なところとか、不可能なところだけに着目してその気持ちを発揮するから、結局は対等になれないまま、その人のできることの方には蓋(ふた)をしてしまったんだと思います。
ですから、同じような温かい気持ちを持って、もしかしたらその人は私と違う何かができるかもしれないとか、私と違うやり方でやればできるかもしれないという目線を持って向き合うことができるかどうか。これがこれからのチェンジできるかどうかのポイントだと思うんです。
だから、親切な気持ちは当然持っていたいし、その着目する目線が大切です。「無理なところ、自分よりできないと思われるところだけに着目することはやめ、視点を変えましょう。」ということなんです。
− 竹中さんのポジティブ精神の源を教えてください。
元々すごい不良で、親不孝の限りを尽くしていました。上に障害がない息子がいるんですが、多分、娘を授かってなかったら不良のままで死んでいたと思います。娘は、35歳ですが、精神発達診断で生後3か月未満と言われています。「彼女が普通に成人するのに、何百年かかるのかな。そうか、人間ってこんなに生きるスピードが違っているんだ。そういうスピードで生きない人がいたんだ。いたのに全然気付いてもいなければ、考えたこともなかった。」ということが分かり、自分としては愕(がく)然としたんです。そして、私も道を外れていて世間からも変なやつとかと言われていましたので、「自分も世の中のレールに乗れなかったという意味では一緒だな。だとしたら、私にこの娘が授かったっていうのは必然かもしれないな。」というふうに考えました。この考え方がいいかどうかは分かりませんが、私はそう感じたんです。
変な言い方ですけど、「自分がすごく解放された。だからいろんな人が世の中にいる。いろんなスピードで生きたり、いろんな生き方をする人がいたりする。」というのが腹の底から分かり、開き直れたんです。例えば私の娘のような存在って、世の中では可哀想とか、気の毒とか、大変とか、マイナスな言い方でしか言われませんが、私にそれを気付かせてくれて、今、プロップ・ステーションをやっているのだって娘を授かってなければ絶対やってないわけです。そう考えると娘はすごい人なんです。「世の中に無駄な人なんかいないし、どんな人にも必ず、その人でないとできないことやその人ならやれることがあるはずだ。」これ、私の中の確信なんです。
だから、「障害があるからマイナス」という考え方自体を変えていこうと本気で言えるのは、私自身が理屈ではなくて、体で確信しているからなんです。実際にプロップ・ステーションをやってみたら、いわゆる障害者と言われている人たちが、「自分たちは障害者じゃなくチャレンジドだという思いで習う側に回る、教える側に回る、サポートする側に回る、助け合いをする。」というこの世界が生まれたわけです。また、仕事と言っても、既存の会社に就職することだけが仕事ではなく、自分たちで起業して、自分たちの働けるシステムの会社や組織とか社会をつくっていくことに彼らは動き始めています。それだけのパワーがある人たちなんです。
これを、わかりやすい事例で言うと、60年前、日本では、「女は外で働けない。政府に参加できない。」と言われてたんです。だけど、女性が「いや、自分たちも男性と同じように社会を対等に支えていける一員になれるし、そうなって当たり前だし、そういう世の中にしないといけない。」と思ったわけです。最初は、そういう人たちは一部でしたが、時間を経るうちに、男女雇用機会均等法ができるなど、法律や社会の意識も変わり、今は女性が働き、男性が家事をしている家庭が出るぐらい、男女がそれぞれのやり方で、社会の一員として活躍するのも当たり前になっています。今、チャレンジドの置かれている状態も、「女性は社会で活躍できません。」と言われていたときと一緒なんです。あのとき、「女性は活躍できません。」という意識とルールによって活躍できなかっただけで、今、結果を見ているとそうではなかったわけです。意識が変わり、ルールが変わればできることが分かった。全く一緒なんです。
この事例を考えてみると、分かりやすいし、教育もそういうことなんだと思います。昔はよき女性というのは、結婚をし、家庭に入り、妻となり、母となり、自分の嫁いだ家に従って、よき子どもを育てるというのが女子教育だったわけです。だけども今は、教育でもそんなこと言いません。つまり、教育というのも時代に応じて変わっていかなければいけないし、いかざるを得ません。
そう考えたときに、チャレンジドに関する教育というのも変わっていくだろうし、今そこの、芽吹きのところを私たちプロップ・ステーションは生み出してやっているってことなんです。今更働いている女性に、「あなた、家庭に戻りなさい。家庭に戻ることが女の道よ。」って言ったって「何、それ。いつの話。」ってことになりますよね。だから、私たちがこういう活動を起こしてやっていく中で、いつか、障害がある人が自分の職場にいたり、自分の近所で何かのビジネスで成功していたりしたときに、「あなた障害者なのに、ビジネスで成功してるんですね。」なんて言うのが恥ずかしいと思えるような時代が来るだろうし、来させないといけないと考えています。そのような社会は、障害があろうが、女性であろうが、高齢者であろうがすべての人たちが力を発揮できる社会とイコールなのかなって思うんです。
もし、本当にそういう社会ができたら、自分の子どもが障害を持って生まれたり、自分の家族が事故などで障害を負ったりしても、そのこと自体は悲しかったり、つらかったりするかもしれませんが、障害があることで、その人の将来が暗いわけはないと考えられます。「この子は障害を持って生まれたけど、あるいは、今あるけれども、将来できることは必ず見付けられて、自分なりに社会で活躍できる。」と思うと家族も別に、つらい、苦しいと言わなくていいわけです。「今はチャンスがないし、障害があったという瞬間から何らかの福祉の恩恵を受けないと生きられません。」というように決めつけられるから、親も何か縮こまるだけだと思っています。「いや、この子にも将来、いろんなチャンスがあるわ。」と思えたら、きっと家庭の在り方も変わると思うんです。
− 最後に、学校現場で日々、奮闘している先生方にエールをください。
今、教育現場ってすごく大変だろうなって思っています。私たちがやっていることはいわゆる学校教育ではないけれども、まさに、教育なんですね。一人一人が、自分の持っているもので光っていけるように。これからの教育っていうのは一人一人がどれだけ自分の得意なことを発見して、そのことで世の中のことを切り開いていくかということがますます重要になってくると思います。
私たちみたいに学校現場ではないけれども、人が人らしく生きていくために集まって勉強する場所にいる者として、立場は違うけれど目指すことは一緒だと思っています。だからお互いに切磋琢(さたく)磨し、悩みがあったら情報交換しながらやっていけたらなと思います。
今、障害がある子の担任になられた先生が、その子を連れて相談に来られることが、とても増えています。だから、先生が全部を抱え込むのではなくて、私たちができるところもあるので私たちを上手く利用して活用してください。それによって、先生方が苦手だと思っていたところも、きっとお互い力を合わせることで、できますよね。私たちはここで理科・算数などは教えられませんが、私たちの得意なことを提供できます。そういう意味でも教育の世界は現場だけでやるのではなく、もっと様々な人を巻き込むとか、自分たちで出向いて行くことで、もっと大きなふくらみを持ってくるのかなと思います。それができなくて全部自分の責任で、結果まで出さないといけないと思ったとき、やはり、先生ってすごくしんどいだろうなと思います。だから、「何かあれば遠慮なく相談を持ち掛けてください。」とエールに代えて申し上げたいと思います。
Wepページ : http://www.prop.or.jp
E-mail : prop@prop.or.jp
※今回はインタビュー形式で取材しました。取材中、竹中さんはバリバリの関西弁で熱く語ってくださいました。