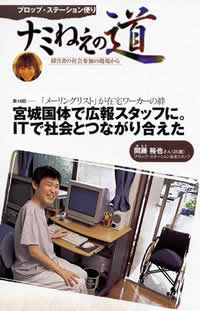|
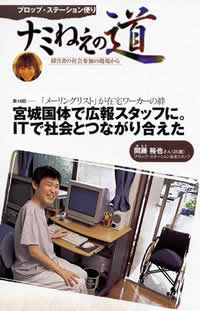 |
|
● プロップ・ステーション
プロップ・ステーションは、1998年に社会福祉法人として認可され、コンピュータと情報通信を活用してチャレンジド(障害者)の自立と社会参画、特に就労の促進と雇用の創出を目標に活動している。
ホームページ
http://www.prop.or.jp/
● 竹中ナミ氏
通称“ナミねぇ”。社会福祉法人プロップ・ステーション理事長。重症心身障害児の長女を授かったことから独学で障害児医療・福祉・教育を学ぶ。1991年、プロップ・ステーションを設立した。現在は各行政機関の委員などを歴任する傍ら、各地で講演を行うなどチャレンジドの社会参加と自立を支援する活動を展開している。
|
全国各地で活躍するプロップ・ステーションの在宅スタッフたち。仕事を通じて深い信頼関係で結ばれている彼らだが、実際に会う機会はほとんどない。主にML(メーリングリスト)(※1)を通じて粛々と仕事をこなす間藤裕也さんは、仙台在住の若きチャレンジド。ITは距離や時間を超えて、チャレンジドらの個性や能力をも生かしている。
初体験の共同作業
「間藤くんと会ったのは2001年に宮城県で開かれた国体のときです。おっとりとした明るい好青年という印象でしたね。宮城国体は福祉に造語の深い旧厚生省出身の浅野史郎知事が、“バリアフリー国体”と銘打った肝入りの大会で、初めて運営面のスタッフとしてチャレンジドが活躍したんです」(ナミねぇ)
地元高校の新聞部の学生が作成した記事を、デジタル化してホームページに掲載するのが彼らの仕事だった。いつもなら障害者は車椅子席に招待されるか、大会後に行われる障害者国体に選手として参加するかのいずれかだったが、本大会での運営スタッフとしての参加は大きな足跡を残したと言えるだろう。間藤さんは生まれつき『ケーゲルベルク・ウェランダー病』という筋肉が発達しない難病、一見すると車椅子で脚が不自由なだけにも見えるが、咳をするにも体力を使うという苦労がある。
「ITの時代に生まれた世代は、たとえ障害があってもこれから勉強も仕事もできます。ぜひ若い世代の代表として、後輩たちの目標になってほしいですね」(ナミねぇ)
●
――パソコン歴は長いですね。
間藤●はい。高校に入学したときにインターネットを試してみたくてPCを使うようになりました。次第に興味が出て、知り合いの勧めでプログラミングの勉強を独学で始めたのは高校を卒業してからです。卒業後は在宅でできる仕事として“テープ起こし”にも挑戦してみましたがダメでした。それからも根気よく在宅でできる仕事がないかとインターネットで探していて、たまたま見つけたのがプロップのセミナーでした。
――セミナーを受講しての感想は?
間藤●VB(※2)の在宅セミナーを受講したのですが、独学では気づかなかったより簡単なプログラミング法を学ぶことができました。ある条件の下で出題された課題にうまく答えられず、安易な方法で解答したとき、今はそういうことを求めているのではないと叱られたことがあります。講師のほかにサポーターが何人かいて、励ましてくれたことが心強かったですね。
――宮城国体について。
間藤●国体開催中にボランティアの高校生が記事にした内容を編集し、HTML化してホームページに掲載するという仕事を広報スタッフとして担当しました。共同で仕事するのは初めてだったので、チーフの指示に従い、仲間の作業を見ながらいいところをどんどん取り入れて作業できたことが現在の糧になっています。また、連絡を密に取ることの大切さも同時に学びました。最近では宮城県主催の「障害者のためのIT講習」の講師を養成するセミナーを1年間受講して、講師の補佐役として教える機会がありましたが、まだ障害者の間でPCは浸透していないというのが率直な感想です。
――現在の仕事と、仕事の進め方は?
間藤●OPEN(※3)上で養護学校の先生方に有益な情報の検索や、リンクの許諾、紹介文の作成などを考えることが主な仕事です。プロジェクトリーダーの中内幸治さん(※4)を中心にMLが作成され、仕事の詳細がそこでやり取りされます。私の技術や体力、性格などを十分に考えて役割分担しています。仕事の内容や納期の指示はすべてMLで公開され、メンバー全員が状況を把握しながら仕事を進めます。
――在宅仕事で苦労することは?
間藤●在宅の場合は誰も管理する人がいないので、逆に仕事の品質が問われるんです。いくら頑張っていると言っても結果が悪ければ言い訳できません。ですから品質をいつも高いレベルに保とうと努力しています。
――今後の目標と後輩へのアドバイスを。
間藤●今のOPENの仕事で、一部レイアウトをデザインする仕事を依頼されたばかり。ちょうどホームページの作成について学び興味を持ったところで、これからはWebデザインも手がけてみたいです。私のように介護が必要で在宅でしか仕事のできない人でも、PCを使えば頭を使う仕事もデザインなど創造力を働かせる仕事も可能です。もっと多くの障害者にPCに積極的に取り組んでもらいたいです。
※1 ML Mailing Listの略で、複数の人と電子メールで情報交換等ができる仕組みのこと。
※2 VB Visual Basic はプログラミング言語の一つ。
※3 OPEN 大阪府下の養護教育諸学校間を結ぶコンピュータシステム。
※4 中内幸治さん SE、プロップ在宅スタッフ。本誌2002年8月号で紹介。
個性さえ生かすITの威力
車椅子の場合、障害が下半身だけなのか全身性なのかは一見してもわからないことがある。要は人のサポートが必要か否かが、大きな差であるとナミねぇは言う。
「下半身だけの障害はもとより、障害が全身性で困難の度合いが高い場合であっても、プロップのチャレンジドのようにITが可能性を開いてくれました」(ナミねぇ)
チャレンジドが積極的に社会に参加し、自分自身を伝えることで世の中を変える原動力になる。一方で本人の性格や家族の雰囲気で一概には言えないのも事実。
「障害の有無に関係なく、引っ込み思案な性格の人が社交的になろうと無理をするのも苦しいだけでしょう。でもITが凄いのは、障害を持ったことで消極的になることなく、そのままの性格で社会とつながる、仕事ができるところ。自分を伝えることのが苦手な人でも、オンラインで出会っただけでお互いがスタッフとしての深い信頼関係を結べる。素晴らしいことですね」(ナミねぇ)
|