| [up] [next] [previous] |
もっと仕事を得るには行政や企業に認知されることが必要 |
| 今のところプロップ・ステーションの支援をしている大企業の仕事が多い。「中小企業の仕事はどうしても急ぎになります。チャレンジドにスピードを期待されたら困ります。
確実にやりますから、速さを期待せんでください、といったら、どうしても大企業の仕事になってくるんです」 先月紹介した以外では、長崎の森正さんがマィクロソフトの在宅社員として働いている。法人向けのホームページに載せる情報を翻訳する仕事をしている。 翻訳は在宅でもできる。インターネットが一般化し、翻訳者の必要性は増えている。プロップ・ステーションではこの秋から新たに「翻訳者養成コース」を設けている。 ちょうど翻訳担当の先生である迫田治さんと服部優子さんがいたので、オールイはこう尋ねた。 「アメリカで開発されて、日本の小さな会社が販売しているようなソフトは、マニュアルの日本語がひどくて、いくら読んでも埋解できません。そういうのが解決されると助かるんですが」 服部さんによると、マニュアルは一般にコンピュータの枝術者が翻訳するケースが多いらしい。自分はコンピユータに詳しいから、わからない人の立場になれないのだ、と。 そういう仕事こそチャレンジドにふさわしいのではなかろうか。 「これからは職安の代行のような仕事が増えてきますから、行政や企業にももっと認知される必要があります。将来は社会福祉法人化を目指しています」(竹中さん) |
 |
週2回のセミナー。(写真提供、プロップ・ステーション) |
すべての始まりは、ナミねぇの長女が障害を持って生まれてきたこと |
| 福祉の世界にもコンピユータ業界にも場違いな感じのナミねぇが、どうして現在に至ったかをかいつまんで紹介する。ナミねぇは神戸生まれの神戸育ち。ただし、両親は九州の出で、血は九州らしい。頬骨が出ているので、確かに南方系の顔だ。私と同じで先祖はジャワ原人である。 プロップ・ステーションは「関西のノリ」だとナミねぇは言うが、物事を深く考える前に行動する体質を私は「九州のノリ」と見る。プロップ・ステーションがうまくいっているのば関西人が上手にフォローアップしているからだろう。 ナミねぇの両親は自由奔放に子供を育てたらしい。 「私が一番上で、下に弟が2人いますが、まともに学校を出たのはいないんです」 ナミねぇは高校1年の夏体みに、アルバイト先の人と恋愛して、一緒に暮らしはじめる。2年のときに、同棲が学校にばれて退学。退学の埋由は「不純異性交遊」。信じられないが、30年前はこんなことに目くじらを立てていたのだ。 そして正式仁結婚。2歳で長男を産み、25歳で長女を産んだ。長女は重い障害を持って生まれた。身体が不自由なぱかりでなく、知能仁も障害があった。母親を認識することもなく、一生を終えるかもしれない(現在は23歳)。 ここから「障害者」に目が開かれていく。手話を覚えて、聴覚障害者の手伝いをしたり、介護ボランティアをやったり。で、日本の障害者はボランティアの都合に合わせて助けてもらう感覚だが、アメリカでは障害者は自分の都合に合わせて、お金を払って人を雇うことに気がついた。 89年にナミねぇは、有料介護を組織化する「メイン・ストリーム」運動を始めた。障害者と介助者を登録し、障害者が介助者を時給で雇うシステム作りである。このネットワーク作りが、やがてプロップ・ステーションに発展していく(プロップを設立した頃、離婚も経験した) ここでわかることは、ナミねぇは、そもそもが「自律の思想」の持ち主なのである。「甘ったれ」や「暗黙の了解」や「日本的な組識の論理」が嫌いなのだ。 ここで私が考えるSOHO本質論に入っていきたい。 |
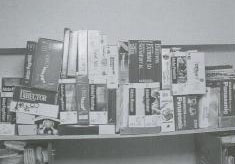 |
技術を身につけるため数多くのソフトを用意している。 |
チャレンジドによるコンピユータグラフィックの展覧会開催 |
||
| プロップ・ステーションのコンピュータセミナー・グラフィックコース卒業生と受講生による、初めてのグループ展が、大阪のツインタワー21で10月1日から31日まで開催されました。 これはインターネットでも公開されています。 URL=http://www.prop.or.jp/challart/menu/index.htm |
||
 |
 |
さいの考察 |
SOHOって、何なんだ |
| 私はSOHOのそもそもの発生の経緯を知らない。というより、アメリカの「シリコン・バレー」のような理想を持って生まれた曼ものだと思い込んでいる。 シリコン・バレーでは、そこにいる自立した工ンジニアたちが、プロジェクトによって、集合・離散を繰り返す。会社のようなビラミッド構造があるのではなく、アメーバのような形のないスタイルなのである。曼荼羅構造といってもいいだろう。少なくともそんな世界観を目指したのが、シリコン・バレーの理想だった。 その世界でば自律あるいは自立の心が「扇の要」なのだ。SOHOがこういう世界観を持ったものでなければ、わざわざ20世紀の末期に登場してくる歴史的意味がないではないか。 たまたまコンピュータという便利な道具が出現して、電話線でつなげば会社に出向かなくても便利に暮らしていける、というだけなら、縄文人のように、竪穴式住居に住んだほうがもっと便利ではないかいね。空気も汚れないし。 ところが今、日本で「SOHO」といえば「下請け」の意味である。独立といってもそれまでいた会社の仕事を下請け的にやっているだけというケースも多い。 それをSOHOというなら、その失敗例を私はたくさん見てきた。私は演劇周辺・活字周辺で糊口を凌いできた人間だ。「編集ブロダクション」「テレビやCMの制作プロダクション」は”SOHO”である。出版社や放送局の仕事をその社屋の外でやってきた。商品を電話線の代わりにバイク便で届けていただけである。 「フリーライター」「フリーカメラマン」「フリ−のディレクター」なども”SOHO”である。これらはすべてバブルの申し子であった。 そう考えると、日本では下請け仕事としてのSOHOの実験は済んでいる。 「下請け」が最後にどうなるかは今の日本を見てみれば明らかだ。「自律」ではなくて「持たれ合い」で食ってきた連中は、今、曼荼羅構造に移行できなくて青息吐息なのだ。「ご縁」で仕事をもらっていた親会社が左前になってくると、親会社と一緒に沈んでいった。 ところが自律のSOHOは、「テレビマン・ユニオン」や「吉本興業」のように放送局と対等に付き合えるし、放送業界では曼荼羅構造の一つの因子になり得ている。それは「フリーライター」や「フリーカメラマン」であっても同じだ。 ナミねぇが考えた「4項目」は、実は日本にSOHOを根付かせる試金石の役割を果たすのである(もちろん、プロップ・ステーションが予想外にカをつけ、ファシズムに走ったら結果は余計悪くなるのだが)。 SOHOといえば聞こえはいいが、この不況の最中にわざわざ下請けに回っている人がたくさんいるような気が、私にはする。 |
| [up] [next] [previous]
|
