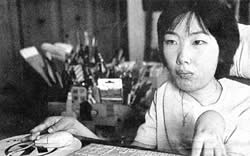| [up] [next] [previous] |
|
神戸新聞 2005年8月30日より転載 |
| 「安心・安全」の街づくり 阪神・淡路大震災から10年 |
||
|
「チャレンジドを納税者に」
|
||
|
民の手に自治を取り戻し
地域、国の仕組みを変える |
||
|
ユニバーサル社会こそ
|
|
|
||
|
阪神・淡路大震災の経験から、わたしたちは多くのことを学んだ。とりわけ安心、安全なまちをつくることは、生活する上でとても大切な営みであることを思い知らされた。そして今、多くの取り組みの芽が育ちつつある。今、わたしたち一人ひとりは安心、安全なまちづくりに向けて何ができるのだろうか。連載を通じて考えてみたい。 |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
「チャレンジドを納税者にできる日本を」
|
||
|
|
||
一つは社会の意識だ。高齢化が進み、家族や親せき、知人に介護が必要な人が増えてきたことで、障害を自分に身近なこととして考えられるようになる人が増えてきたという。「ひと昔前だったら、家族に障害者があればそれをひた隠ししていたが、今はそんなことはない。プロップにも、障害を持つ小さな子どものご両親が、この子の将来のために今から親に何ができるか相談に来られます」 もうひとつの変化はIT(情報通信技術)の普及だ。パソコンを手にしたことでチャレンジドの就労の可能性が広がった。そして、インターネットを通じてさまざまな人とのネットワークが広がり、同じ悩みを共有できる人とのつながりができた。 「パソコンを手にしたことで、チャレンジドの人たちが、初めて人間らしくなれた、と言います。まさにパソコンはチャレンジドにとっての打ち出の小づちなのです」 去る6月に国会で成立した改正障害者雇用促進法では、障害者雇用の対象として在宅勤務者も認められることなども盛り込まれた。竹中さんが長年訴え続けてきた成果の一つだ。潜在的に働ける力のある多くの障害者の雇用につながることが予想される。 「経済と福祉は表裏一体」と竹中さん。経済が安定してこそ福祉が豊かになる。一人でも多くの人が働く側に回れば、真の福祉が実現する。 「だとすれば、一人でも多くの人が経済活動に参加し、よき働き手であるとともに、よき消費者であることが大事なのです」 |
||
|
|
||
長女・麻紀さんは生後間もない3ヵ月検診のとき、医師から重い脳症と言い渡された。周囲は「不幸の極み」ととらえた。「不幸なんて勝手に決めつけないでほしいと思いました。わたしはかなりの不良でしたが、そのことで親を不幸にはしたくはなかった。娘も同じ思いのはず。人間一人ひとりにはそれぞれのものさしがあっていいんじゃないかと思います」
|
||
|
|
||
「世の中を変えようと思ったら、自分の意識がまず変わらないといけない。そして、周りに関心をもってもらうこと。それから科学技術などの道具をうまく生かすことを考えなければならないし、法律制度も必要になってくる」 |
||
|
|