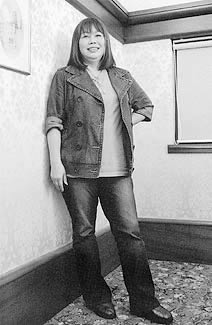|
 |
竹中ナミ(たけなか・なみ)
社会福祉法人
プロップ・ステーション理事長
1948年神戸市生まれ。73年重症心身障害を持つ長女を出産したことから障害者の福祉や教育を独学、さまざまなボランティアに取り組む。91年には障害者の自立と社会参加を目標に、パソコンなどITを活用し就労促進を目指す団体「プロップ・ステーション」を設立。障害者と企業、自治体の橋渡し役に。99年エイボン女性年度賞教育賞、現在、各行政機関の委員や大学講師なども務める。著書「ラッキーウーマン」など。 |
| 本文中で再現した「ちゃきちゃきの関西弁」は陽気なナミねぇのトレードマーク。東京での重要な会議の後、やはりトレードマークのジーパンスタイルで颯爽と対談場所に現れました。いま大阪の街と人を元気にするために、親友であり弁護士で大阪市助役の大平光代さんと「みっちゃん&ナミねぇ」のコンビで頑張っているそうです。 |
田中豊蔵(たなか・とよぞう)
ジャーナリスト
1933年東京都生まれ。朝日新聞政治部記者として自民党や政権中枢の取材を長く担当した後、調査研究室長などを歴任。91年からは同社取締役論説主幹に就任し、朝日新聞の社論を代表した。現在はジャーナリストとして政治から社会、教育などを幅広くテーマで活躍中。1990年より財務大臣の諮問機関である財政制度審議会委員を務めている。 |
|
|
|
「保護や救済の対象でしかなかった障害者を
ナミねぇはチャレンジドに変えた」−−田中 |
|
田中 竹中さん、いやナミねぇといわせてもらいます。ナミねぇは障害者の問題を突破口として社会福祉運動に独自のジャンルを切り開いてこられた。障害者を社会の一員に加えていくにはどうしたらいいか。このテーマに打ち込んできたナミねぇは知る人ぞ知る有名人で、『20世紀を彩った女たち』という本にも紹介されているほどの女性闘士ですが、きょうは改めてご紹介したい。
竹中 できれば21世紀を、と呼ばれたかったんですけれども(笑)。
田中 ナミねぇは、これまで障害者と呼ばれていた人たちを、「チャレンジド」と前向きな言葉に置き換えた。そうした問題意識からお話しいただけますか。
竹中 はい、わかりました。日本語で、障害者は、「障」の字も、「害」の字も、ネガティブな意味合いですよね。つまり「こういうことができない気の毒な人」というマイナス面に着目した呼び方なわけです。アメリカでもこれまでは、やはり「ハンディキャップド」とか「ディスエイブル・パーソン」とか。
初めて「チャレンジド」という言葉に出会ったのは、あの阪神淡路大震災の直後でした。アメリカで「マイナスにだけ着目してその人を表すなんておかしいのでは?」という声が上がって、「The
challenged」という言葉を生み出した。聞くと、「神様から挑戦という使命や課題を、あるいは、挑戦するチャンスや資格を与えられた人たちという意味なんだよ」と。
私、頭をガーンと殴られたような気持ちでした。しかも、大震災で家を全焼して、プロップ(ステーション)の仲間たちも全員被災、まさに自分たちがどん底に置かれていたとき、「震災復興に立ち向かう人をチャレンジドだっていう表し方もするよ」って聞いたとたんにね、元気が出たんです。
田中 「プロップ・ステーション」の名前の由来も教えてください。
竹中 「プロップ」はラグビーのポジションからなんです。私と一緒に活動を始めた仲間にスポーツ事故で首の骨を折り全身麻痺になった青年がいて、彼がラグビーをやっていたときのポジションが最前列でスクラムを支えるプロップだった。同時に、その言葉に、「支柱」とか「つっかえ棒」、「支え合い」という意味があったんですね。
これまで日本では、障害者は支えられる人で、障害を持っていない人が支える立場でした。私たちの活動趣旨は、「お互いできるところを出し合いっこして、できないところを支え合いしていこう」「障害のあるなしにかかわらず、得意なことを世の中に発揮していこうよ」ですから、ああ、これはピッタリだなと。
田中 その「プロップ・ステーション」を立ち上げたのはいつですか。
竹中 1991年の5月です。そのころまだコンピュータは一般家庭になかった。ところが、全身に障害があって家族の介護を受けている方から「これからコンピュータのような道具が自分たちの働く武器になる」と、アンケートに回答を寄せてこられた。そこで今までと違う福祉活動が展開できるかもわからへんとひらめいたわけです。
田中 そこから、「家族や施設が面倒をみる」「年金や給付で静かに暮らす」といった、保護や救済の対象にしかしない従来の考え方から、ナミねぇ自身もガラッと転換した。IT時代にコンピュータというツールを生かして働きたいと願う、まさにチャレンジドのためにね。
竹中 合言葉は、「チャレンジドを納税者にできる日本」。ただ、日本の税は彼らからは取りたくないというか、取らんでもええという仕組みになってます。ですから税のシステムを見直して、たとえわずかではあっても、タックスペイヤー(納税者)になれる方にはなっていただくという仕組みにしないといけません。
|
「『障害者をタックスペイヤーに』の合言葉は
ケネディ大統領が言い出しっぺでした」−−竹中 |
|
田中 だれでも税金は安いほうがいい。タダなら、なおさらいいんじゃないですか。
竹中 いや、そうでもないんです。それと私、関西人ですから、人の力を眠らせている状態が、もったいのうてしゃあないんですよ。他人のサポートや機械の力があればできるのに、障害者というだけでできへんって決めづけられると、その人は悔しいというか社会に対してすごい反発を招く。
田中 そこに新しい手を差し伸べたのがプロップの活動ですね。働いて応分の税金を払うことで、自分の生きがいが証明される。
竹中 そう。だから、私たちがやっていることは「誇り取り戻し運動」だと思ってます。税を払うことを目的化しているわけではなく、自らがその社会に守られるだけではなく、人の役に立ったり、期待に応えたり、支える側にも立つ−−これって人間の誇りの根源じゃないですか。でも、「あなたは期待されない人よ」と言い渡されているわけですよ、いまの日本では。
この「障害者をタックスペイヤーにしよう」っていう言葉は、私が言い出しっぺじゃなくて、ケネディ大統領が就任後初めて議会に提出した教書の中に書かれています。「税金を払わんでもいいよ」とか「あんたら、払うの無理やろ」って決めつけることのほうが差別で、「払えるようにする」って国家が意志を持たないといけないという、あのケネディの言葉が私をすごく変えました。
田中 去年アメリカへ行って来られたんですね。
竹中 はい。ワシントンDCで行われたチャレンジド政策を議論する官僚会議に、日本からオブザーバーとして招待していただいたんです。官僚会議ですから、日本でいうと霞が関の各省庁から来た幹部がズラッと並んでいるという感じで、その25人のうち半分が女性。その中に7人の重度のチャレンジドがいて。それも盲導犬や介助犬を連れてらっしゃる方、全身麻痺で電動車椅子に乗っている方、あるいは聴覚障害で手話の通訳やノートテイクがつく方々など、みなさん官僚エリートなんですよね。
田中 日本はまだまだ・・・・・・。
竹中 ただ、日本はアメリカより社会保障は進んでいるんです。ですから、その上に自分の力でチャンスをつかんでいける仕組みの両方を合わせると、素晴らしい制度になる。いま壁にぶつかっているのはなぜかと考えると、「あなたたちは障害を持っているから、下駄を履かせてあげましょう」と下駄だけプレゼントして上に進めるチャンスがないからです。チャンスをというと、議論の方向は「下駄を高くしてください」となる。これがモラルハザードの出発ですよね。
それは地方自治体の分権の話でもそうだし、たぶん高齢者や女性の問題に対しても一緒なんです。
田中 なるほど。
竹中 ところで、ワシントン大学の在籍者の7%がチャレンジドの学生、全米平均でも4%なんですよ。日本は、それに比べて0.09%しかない。古い言葉ですが、日本のチャレンジドにとって大学はまだ「高嶺の花」なんです。
田中 いまピンときたのは、難病で車椅子生活を余儀なくされているイギリスの著名な物理学者のホーキンス博士。世界第一級の頭脳の持ち主ですが、隠れた才能は日本にもまだいるかもしれない。
竹中 ただし、世の中そんな天才的な人ばかりじゃないので、普通に同じ土俵で社会に参画できるというふうになってほしい。それには法律の力と、人のサポートの力と、ITの力、やっぱりこの三位一体が大切です。
 |
|
「いまの私に育ててくれたのは脳障害の娘
私からするとすごいやつなんです」−−竹中 |
|
田中 ガラッと話が変わるんですが、竹中さんが自分のことを「ナミねぇ」と呼んでくれと言う。その原点は、10代のころ女番長だったキャリアにあると……。
竹中 いまもそうなんですけど(笑)。
田中 そのナミねぇが書いた『ラッキーウーマン』を読むと、その不良少女は警察に補導されたことが4回あって。
竹中 ええ、4回どころじゃないですね(笑)。
田中 私はすごいと思う、現在の素晴らしい仕事と若いギャップが。なにが現在の竹中さんをつくったんですか。普通だったら、グレた女性で終わってもおかしくない。
竹中 はい。でも、元不良だったから、いまみたいなことがやれてるという側面もあるんです。私、もともと世の中が正しいとする道に向かって、よう行かないとか、これは違うぞとか、自分には向いてないとか、勝手なことを思っていた。だから、「よい子」っていう道がまっすぐ先にあるのは知っているけど、「こんなふうに生きたくない」「きっとほかに向いたことがある」と夢見て、アウトローの世界に近づいたわけです。最終的にはそのアウトローの人たちから、「あんたはこれ以上こっちきたらあかん」って追い出されたんですけども。
田中 アウトローの人にも、いい人がいたんですね。
竹中 あの当時はワルというても、ホンマもんのワルと、ワルもどきっていう間に一線あったんです。この線を越えるのはすごいことで、向こうにあるのは麻薬と売春と殺人でした。この線を越えていくのはよほどのことだったんです。
ところが、いまはこの3つが日常の中に近づいてきて、小学生のそばにまで来てる。だから私は昔の不良でよかったし、「違う価値観を持ったってええやんか」と道を外れたことが、ある意味よい人との出会いにつながったという思いがあります。
それと、私を更生させた最大のものは、やはり自分の娘なんですね。
田中 麻紀ちゃん。
竹中 勉強が嫌いで学校行くのも嫌やった私が、自分の娘が重度障害とわかった瞬間に、大学の図書館とかに通いだして脳やら遺伝子の勉強を始めた。あんなに勉強する気になったことなかったですわ。「まず知識と情報を得やんと、次に自分が何をしたらいいか見つからんわ」となった。それを教わったのは自分の娘だったわけです。
だからいま勉強が嫌いっていう子には「嫌いでもええよ」と言うんですよ。「困ったら自分から勉強する気になるから、困るまで遊んどったらええわ」って。たぶん人間は、自分が学びたいなあと思ったときしか本気で学ばないんだと思う。いま子どもたちにあらゆるものが与えられていて、自分が何に困っているのかすらわからない状態です。ものすごく大変やろなと思いますね。
そういう意味では、自分の娘は重症の脳障害ですが、彼女が人を騙すことも、傷つけることも絶対あり得ません。しかも、いまの私に育ててくれたのは彼女ですから、私からするとすごいやつなんです。
|
「人によって力やスピードは違って当然
身の丈に合う出し方ができる社会に」−−竹中 |
|
田中 きょうの対談はただ感心することばかりです。でも実際に自分の子どもが重度障害者になったとき、それを乗り越えるには精神的にも経済的にも大変じゃないですか。
竹中 そうですね。とくに体力的に大変やと思うんです。私、いまこんな太ってますけど(笑)。娘の介護をしてた20年ぐらいの間は、平均睡眠時間が2〜3時間でした。
障害児のお父さん、お母さんをたくさん存じ上げていますが、障害のある赤ちゃんが産まれたことにショックを受けて、連れて死んでいった方もいます。だけど私はずっと生きてきたので、彼女が授かったとき、ある意味で当然という気分があったんです。これだけ自分が道を外れてきたら、自分に世の中のルールとまったく違う存在が与えられても、べつに不思議じゃない。
ものすごく不遜なんですけど、それで解放されたんです。そして力が湧いてきた。
田中 そういうナミねぇの生きざまに多くの人が心を打たれて、プロップを応援しているんだと思います。
竹中 いやいや、時代の変わり目に、なんか変なやつが現れた、その変なやつの求めている気持ちが、いろんな分野の中にいらっしゃる方と共通するものがあるからではないですか。この共通のキーワードは、「危機感」なんですね。私の支援者には危機感を持たない人は一人もいないんです。「日本、このままでは大変よ」って・・・・・・。
田中 竹中さんはいろんなところで、「社会のほうを変えたらええねん」と言う。これもナミねぇのキーワードですね。日本はいま、政治や経済、行政、外交、あらゆる面で社会のほうをどう変えるかっていう、瀬戸際に来ている。どういうところをどう変えたらいいですか。
竹中 それは、人の力をどう引き出すかっていうシステムに徹底すること。マイナスのところを埋め合わすっていう考え方から、可能性を全部引き出すほうに転換したらいい。要するに、その人の身の丈に合った力の出し方をすればOKだ、と。
人によって出せる力の量やスピードは違って当たり前ですよね。つまり、10出せる人は10出せばいい。全員10出さなあかんと思うから、1の人を排除するけど、1の人が1出そうと意志を持つことは貴重である、という考え方です。
その代わり、10出す人は10出してちょうだい、と。この人たちがサクセスをつかんだり、お金持ちになっていかれることは全然OKです。だけど、1出した人が1に見合った収入を得て、そして1に合ったちゃんとした社会的地位を得られることが大事。そうしてだれかがゼロになったとき−−10の人だって、いつかゼロになる可能性はあります。その場合には、みんなの総意の下にその人たちを守られるという・・・・・・。
この社会のシステムを私、「無血革命」って呼んでるんです。
田中 竹中さんの話を聞いて、勇気づけられる若者や女性が多いんじゃないかな。きょうは本当にありがとうございました。
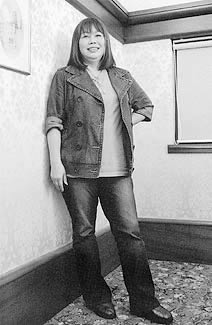 |
|
|