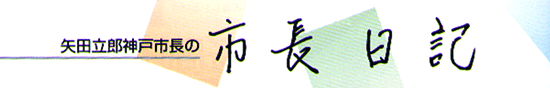
 |
| 「スワンベーカリーKOBE」で、つくりたてのパンを購入する矢田立郎市長 |
| 5月17日 |
「スワンベーカリーKOBE」がきょう開店し、そのオープニングセレモニーに私も出席した。スワンベーカリーは、クロネコヤマトの小倉昌男会長が福祉財団をつくり、その財団の事業として、障害者がみずから働くことによって生活費を稼ぐ。最低でも月に10万円ぐらいの収入が得られるような事業をめざそうと、有名なベーカリーと手を組んで始めたパン店である。今では全国に十数店舗あり、その神戸の第1号店として長田区大正筋の再開発ビルでオープンしたわけだ。
スワンベーカリーになる前は、以前から地域の中で障害者の生活支援をしているNPO法人が中央区で別のパン店を運営していたが、経営的にも非常に厳しかったため、この際スワンベーカリーのような全国的に注目を集めているグループの一員に加えてもらって、心機一転を図ろうと。そして私からも小倉会長に口添えをしてほしいと頼まれ、実は全然面識はなかったのだが、私から小倉会長に直接電話をさせていただいた。
その長田で新しく店開きをすることは、
障害者の自立支援と震災復興の二重の意味でたいへん意義のあることなので、ぜひ配慮をしてほしい
と言うと、「分かりました」と言っていただいた。ただし、その時も小倉会長は、「きちっとした商売ができますか? 私どもは実際に障害者の人に10万円ぐらいの賃金を払う前提で事業を進めているので、店舗の立地・規模などについてもかなり厳しく選別しています」と言われた。障害者の真の自立に向けても、スワンベーカリーの経営は厳しいことを言外ににおわせておられた。
たしかに、かつては障害者の自立といえばとかく国とか、公共団体の補助の話になるケースが多かった。それが今や、情熱をもったリーダーがまず事業を起こし、その事業を成功させることによって障害者が自立する方向に向かっている。すばらしいことだと想う。
私は以前から折に触れて“親亡きあと対策”ということを言ってきた。これは、障害者が両親と一緒に一生過ごせたらいいけれど、人間はどこで必ず両親と別れるときがやってくる。そのときに、どんな支援ができるのかをみんなで考えなければいけないという問題である。障害の程度によって施設が必要な人もいるだろう。地域によってはグループホームのような仕組みがあり、その支えを受けてやっていくことも考えられる。あるいは、何らかの就労場所があり、地域で皆に見守られながら暮らしていくのも一つの方法だ。いずれにしても、
就労の場所があって、それぞれの能力に応じて収入を得ることができればそれが一番いいわけで、
就労支援に対する認識が高まってきたのは当然のことと言える。それだけに「スワンベーカリーKOBE」にはぜひとも頑張ってもらい、地域の人々に愛されるいい店になってほしいと心からの声援をおくりたい気持ちでいっぱいだ。
このスワンベーカリーと同様の考え方で進めている事業は、神戸にはほかにもある。その一つは、竹中ナミさんの行っているプロップ・ステーションだ。六甲アイランドのファッションマートを拠点にして、障害のある人たちが高度のIT技術を持つことによって在宅でも仕事ができるようにし、税金が納められる自立した生活をめざして頑張っておられる。ここではコンピューターの初歩からプロになるところまで一貫しており、一人前の技術を身に付けた多くの障害者が全国にいて、ネットワークを組んで在宅で仕事をしている。仕事はプロップ・ステーションが受注し、それをそれぞれの能力に応じて出す形にしているので、自治体の補助とかを当てにしなくても比較的安定しているようだ。
また、フェリシモといって全国に多くの顧客をもつ通販の専門企業が中央区にあるが、ここの矢崎和彦社長と竹中さんは、私が市長に就任してスタートさせた政策提言会議のメンバーになっていただいている関係で、その場で「障害者のために何かしよう」という話になり、フェリシモとプロップ・ステーション、兵庫県、神戸市が合同で「チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト」をつくり、昨年から事業を行っている。
その仕組みは、小規模作業所とか授産施設などで制作される商品を、実際の流通に乗せて問題がないかどうか審査までして品目を決め、これなら大丈夫という物を選んでカタログやインターネットで販売をする。従来の障害者の人たちが行っていた物販のシステムや考え方とはまるで違う、まさにインターネット上で情報が飛び交う中で商品を選んでもらい、販路を拡大していくというもので、まさしくこれは革命ではないかと私は思っている。
障害者を取り巻く環境は時代とともにどんどん変化している。その中で、
たとえハンディキャップがあっても、それを特性として、持てる能力をすべて出せるような社会にする
ことが大事であって、そんな世の中に一日も早くなるよう神戸市としても取り組みを進めていきたいものだ。
 |
「チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト」でインターネットにのせる商品を見る、右から矢田市長、竹中ナミさん、矢崎和彦さん | |
|
||
