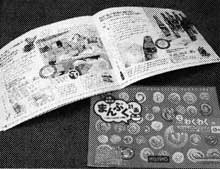|
|
家にいながら買い物ができる通信販売(通販)。病気やけがで外出できない人も利用できるという点で、年齢、性別、障害の有無などにかかわらず使いやすい「ユニバーサルデザイン」(共用)的な仕組みだ。この考え方を拡大し、商品開発やサービス展開に応用する動きが活発化している。通販業界の"ユニパーサル化"を迫った。
(安田 武晴)
|
|
 |
「チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト」の作品展示会で出来栄えについて意見を交わす参加者たち。ユニパーサルデザインの考え方を取り入れたこのプロジェクトから、全国に売り出せる通販商品が生まれた(神戸市で)=桝田直也撮影 |
|
※異彩放つ
|
|
「一年間わくわくが続く 年間予約コレクション」。カタログ通販会社「フェリシモ」(本社・神戸市)が、先月中旬から全国で発行している商品力タログだ。
掲載商品は食品や雑貨、絵本など計三十三点。どの商品も一度申し込めば、月一回ずつ一年間(一部商品は半年間)にわたり商品が届く。「つるつる麺紀行」という商品は、毎回、産地の異なるそばやうどんなどが楽しめる。
定番商品が並ぶ中で、ひときわ異彩を放つ商品があった。一つは「ぐるぐるうずまきクッキー」。毎月、色や大きさの異なる渦巻き型クッキーが、かわいらしい水色の小箱に入って届く。もう一つは、「さをり織り雑貨と手づくり小物」。伝統や決まり事にこだわらない「さをり織り」のミニバッグ、手帳カバーなどが、ハーブせっけん、再生紙で作ったカードなどと一緒に届く。
これらを作ったのは、実は障害者たち。カタログに載った商品は、障害者の就労支援を行う社会福祉法人「プロップ・ステーション」(神戸市)、兵庫県、神戸市と同社が今年一月に始めた「チャレンジド・クリエイティブ・プロジェクト」の第一弾なのだ。
|
※競争覚悟
|
|
「チャレンジド」とは、「挑戦という使命や機会を与えられた人」という意味で、障害者のこと。プロジェクトでは、障害者の授産施設や作業所を「アトリエ」と位置づけ、そこで作られた製品を、通信販売で全国に流通させる計画という。
参加しているのは、呼びかけに応じた四十五施設の中から選ばれた兵庫県の十三施設。全国に流通しても恥ずかしくない商品にするため、デザインや品質などで市場競争に堪えるよう、フェリシモ社員がアドバイスを繰り返した。
同県伊丹市の知的障害者通所授産施設「ゆうゆう」を訪ねると、全国流通を前に、商品を作る手にも力が入っていた。
「ゆうゆう」では、クッキーやハーブせっけんなどの注文を受けた。いずれも、普段作っているものより形が複雑だ。久野茂治施設長は「『障害者が作った商品』ということで買ってもらうようなやり方は通用しない。生産事業者として、きっちり仕事をこなさなくては」と話す。クッキー班の倉橋正光さん(54)も「たくさん売れるよう一生懸命に作る」と表情を引き締めた。
|
|
商品が掲載されたカタログ
|
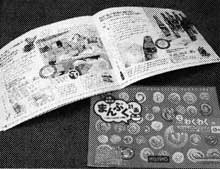 |
|
※共生へ
|
|
そもそも自宅から誰でも注文できる通信販売は、それ自体がユニバーサルな販売形態。「その中で、ユニバーサルデザインの商品(共用品)を扱うだけでなく、生産手段を含めた総合的なユニバーサル化を考えた」と、フェリシモの矢崎和彦社長は解説する。
プロジェクトによって、通販業者にとっては優れた商品が新たに開発された。一方、これまで授産施設付近の顧客向けに細々とクッキーなどを焼いていた障害者にとっては、障害の有無にかかわらず能力を発揮できるという意味で、「ユニバーサル(共生)社会」に一歩近づいた。
誰が作った商品でも、いいものは全国に流通させるー。このプロジェクトは障害者だけでなく、流通手段を持たない生産者にとって、大きな可能性を与えるものでもある。
|
| ユニバーサル(共生)社会 年齢や性別、障害の有無などにかかわらず暮らしやすい社会のこと。だれでも使いやすい商品を作る「ユニバーサルデザイン」(共用品)の考え方を拡大した。サービスや社会資本整備など幅広く応用可能な理念で、特定分野で実施する場合は「ユニバーサル化」と表現する。 |
| 障害者の授産施設・作業所 企業などで働くことが難しい障害者に作業を提供し自立を促す施設。授産施設は法律に基づく施設で全国に約2000か所、作業所は法律に基づかない任意の施設で、全国に6000か所以上ある。 |
|
|
|
|