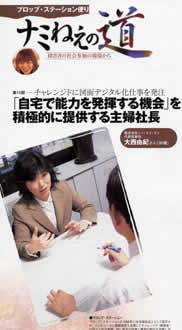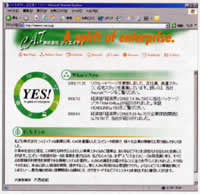|
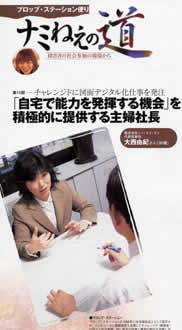 |
|
● プロップ・ステーション
プロップ・ステーションは、1998年に社会福祉法人として認可され、コンピュータと情報 通信を活用してチャレンジド(障害者)の自立と社会参画、特に就労の促進と雇用の創出
を目標に活動している。
ホームページ
http://www.prop.or.jp/
● 竹中ナミ氏
社会福祉法人プロップ・ステーション理事長。重症心身障害児の長女を授かったことから 独学で障害児医療・福祉・教育を学ぶ。1991年、プロップ・ステーションを設立した。現
在は各行政機関の委員などを歴任する傍ら、各地で講演を行うなどチャレンジドの社会参 加と自立を支援する活動を展開している。
|
ITの活用でチャレンジドの就労促進と雇用創出を目指すプロップ・ステーションにとって、ビジネスパートナーは欠かせない存在だ。大阪市淀川区にある株式会社シィ・エイ・ティはデジタルソリューション事業の分野で注目の企業。一介の主婦だった社長の大西由紀さんが、ITを活用して目指す理想の社会は、立場こそ違うがナミねぇと相通じるものがある。
初対面で意気投合
「ナミねぇ」「由紀さん」とお互い気の置けない関係になるまでに、それほど時間はかからなかったという。8歳と5歳の二児の母親であり、加えて主婦業と社長業の一人三役をこなす大西さんだが、女性社長という気負いは微塵も感じられない。
「由紀さんはおきゃん(※)で、少しおっちょこちょいなところが私に似ていると思います(笑)。芯が強くて、とても魅力的な女性。子どもに対して愛情が深い分、仕事と家庭の両立に気持ちが揺れることも多かったのではないでしょうか」(ナミねぇ)
主婦が子育てをしながら安心して働ける社会には、日本はまだまだ程遠い。1999年に実施された女子雇用管理基本調査(旧労働省)での育児休業を取得した女性労働者(正社員を対象)は約56%と、欧米と比べて低い水準にある。ITを利用して、たとえば在宅ワークなど雇用以外の働き方のできる人たちが、社会で活躍できるシステムや法律が待ち望まれている。かたやNPOの代表としてチャレンジドの、かたや企業人として主婦の就労促進と雇用創出を目指す。
※おきゃん……元気でおてんばという意味の言葉。
主婦を納税者に
――ナミねぇと知り合ったきっかけは?
大西●プロップ・ステーション理事の成毛眞さん(株式会社インスパイア代表取締役)が、すごい人に会わせるからって紹介してくださいました(笑)。ナミねぇは迫力と強さのなかで、人に対して常に何かを与えているというイメージが第一印象でした。それ以降、仕事をお願いして以来、プロップさんはとても信頼のおける発注先です。
――そもそも起業した理由は?
大西●OLをしていて結婚退職。専業主婦も楽しくこなしていましたが、時間を何かに使いたい気持ちが強くなり、CADの技術を修得して派遣で働き始めました。そのうちIT化が進むにつれて、CADの分野はこれから伸びる業界だと起業を決意したんです。
――主婦にとって社会進出は?
大西●とても厳しいですね。たとえば、子どもに少しでも熱があれば保育園も預かってくれません。特に、最近は不景気でどこの家庭もご主人のリストラや減収の不安を抱えています。先日もハロワークで一般事務の募集をしたところ、80人の応募がありました。それだけ働く場を求めている主婦が多いにもかかわらず、年齢制限や残業などの諸条件でなかなか職場が見つからないのが現状ではないでしょうか。
――ITの可能性について。
大西●今やパソコンは一家に1台あるというほど普及しましたから、技術を磨けば在宅での仕事は十分できると思います。主婦業のかたわら好きな時間に適量の仕事をこなすことで時間を有効に使えます。また、弊社でも資料をメールで送信し、仕上がったデータをメールで納品する方式ですから、全国各地に仕事を委託できます。技術の進歩は目を見張るものがありますが、一方で在宅ワーカーへの精神的なケアやフォローも見落とせないと思っています。
――これからの抱負を。
大西●ITを有効に使えば主婦であれ、チャレンジドであれ、地方にいる方であっても、自分の能力を自宅で発揮できるという世界がさらに広がることを期待しています。そのために起業してから10年間培ってきた効率化等のノウハウを、企業にも働く側にも積極的に提供していきたいですね。
――チャレンジドへの仕事の依頼について。
大西●プロップ・ステーションにはこれまで10件以上、約10人のチャレンジドの方に仕事をお願いしました。しかも短い納期で発注したにもかかわらず、納期よりも早く、その上ほとんど修正を加えずに済む出来栄えでした。また、障害者交流センターのホームページ制作を依頼したときには、実際に車椅子を使っている写真を撮影して掲載したり、文字を大きくして高齢者などにも見やすいよう細かく配慮して制作していただきました。ITを通じて何の隔たりもなく、むしろチャレンジドの方々の集中力や能力の高さに驚かされます。
 |
|
社内のスタッフと一緒に。
|
在宅ワークを推進
働いている女性の多くは、子どもの問題で少なからず常に悩みを抱えているという。また、働きたくても社会の状況で働けないという現実は、チャレンジドが直面する状況と似ている。
「コンピュータのソフトやハードの進化によって、今まで困難だった仕事が容易になってきました。あとはすべての人にチャンスが与えられる環境づくりが急務だと思います」(ナミねぇ)
また、企業や自治体がもっと在宅ワーカーやその人たちを支援する企業や団体に目を向けることも必要だとナミねぇは話す。少子高齢化社会の日本では、フルタイムで働ける人の比率が急速に低下しつつある反面、年金受給者は増えている。
「今やプロップのCADの牽引役としてシィ・エイ・ティさんの仕事をお手伝いしているチャレンジドも、かつて入退院を繰り返して難病を克服したという経緯があります」(ナミねぇ)
在宅であれ、短時間であれ、ITを活用した多様な働き方で、誰もが社会を支える存在として誇りある生き方のできる社会へ。その声は日増しに高まっている。
|