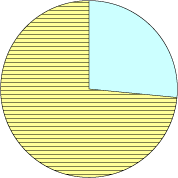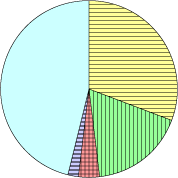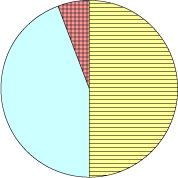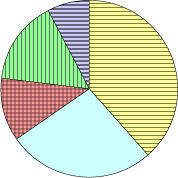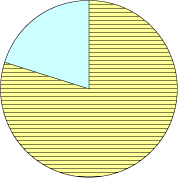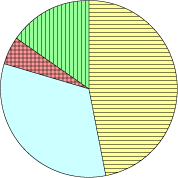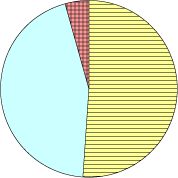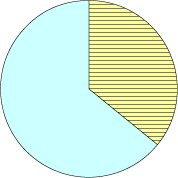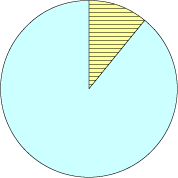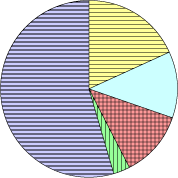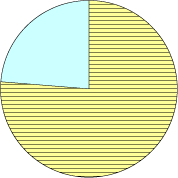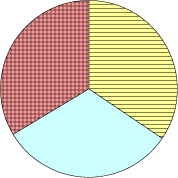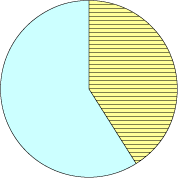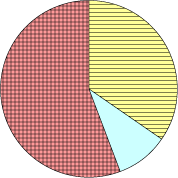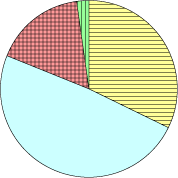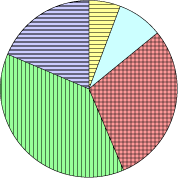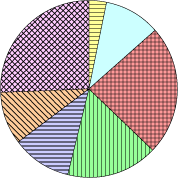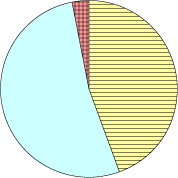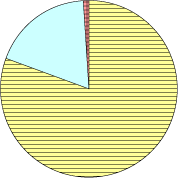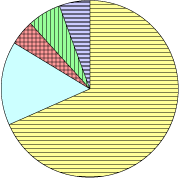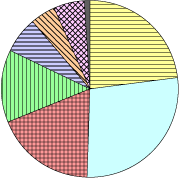|
現在の日本社会では、まだまだ障害者に対する様々な配慮が欠けております。私自身がその身になって、はじめて考える事が沢山あります。国の政策、会社の対応など、障害者の積極的な気持ちを踏みにじるやり方が多く見受けられるのではと思います。特に生活の保証の点に関しては、身体が元気でなければ生活していけない社会構造になっており、障害者の持っている他の能力を活かす場が少ないような気がします。アメリカ、ヨーロッパの社会を研究し、個人ではなく団体として活動し、力をつけるべきです。
(男 41才 直腸機能障害 2種4級)
障害者が仕事を持つことは、納税者になり国の台所を潤すことになる。なぜそのことが国や多くの企業には分からないのだろう。肉体的な仕事に向かない障害者でもOA機器を駆使して幾らでもできる仕事はある。通勤できなくても通信網の発達により仕事はできる。では、なぜ障害者に仕事が来ないのか、雇おうとしないか。それは、世間の障害者に対する概念が、低知能、低能力、ひ弱という事になっている。だから職安に行ってもまず聞かれる事は「字が書けますか」だ。
しかし、障害者の側にも問題がある。年金貴族と呼ばれる人たちである。仕事をすることによって年金の額や手当が減るという事から、仕事をしない方が生活が豊かで身体も楽だとなれば、就業という二文字は必要ないのだろう。「生活が苦しいから年金を上げろ」という運動と、「豊かな生活をするためにも仕事を与えろ」という運動の関係は相反するものではなく、障害者の生活を豊かにするという観点から見れば同じことである。問題は「働くことにより、年金が減らない」ような制度にすることと、企業が必要とする能力を持つことであろう。完全雇用と言っても、やはり健常者との体力の差は大きく、それだけ働く期間が短い。それらの事が加味された障害者の雇用制度の確立を国および企業に強く望みたい。
(男 41才 頸髄損傷 1種1級)
日本人、特に若者が自己中心であるのが最近目立つように思う。電車内の優先座席には大抵若者が座っており、私がそばに立っても立上がって代る者はあまり居ない。代ってくれる人は中年の人が多い。障害者の就業については、罰金を払って済ます方がマシという会社が多いので、違反すれば懲役刑(会社幹部)にすべきだ。
(男 59才 両下肢麻痺)
健常者でも少ない技術力を持っている人を、障害があるという理由だけで採用を断る企業が多い。こんな企業の態度を改めるために、障害者雇用促進法ができたはず。実際に効力を発揮していると思えない。 日本では就職できる地域によって仕事の内容が変わるが、工業中心の所では障害者の就職は難しい。
(男 33才 頸髄損傷)
いくら才能があっても重度な障害を持っているために就職が出来ない場合が多いのではないでしょうか。コンピューターが普及によって、それを利用して少しでも自分の可能性を活かされないかと考えています。
(女 26才 脳性麻痺)
企業が障害者を雇用する時、法律による義務とその優遇措置による所が多く、おざなりの仕事と低賃金に甘んじざるを得ない。障害者であっても、企業人としては一般人と同等の権利と義務を負うべきであり、企業に貢献すべきである。福祉事業と混同している障害者も雇用も壁の一因である。企業は両者にプラスになる障害者職種を開拓し雇用するべきで、場当たり的な雇用すべきでない。
(男 33才 両下肢麻痺)
これまでの障害者雇用は、障害者といっても、軽度の人のみに限られてきました。これからは、重度障害者でも働く意欲と能力のある人へもっと雇用の場を広げる必要があると思います。その為には、受け入れる側、障害者共に意識改革が必要だと思います。
(男 28才 C4、5脱臼骨折 1種1級)
障害者が社会参加できるように国や企業が積極的に支援してほしい。
(男 36才 脊髄性素硬化症の疑い 1種1級)
これまでの会社の経験から、本人にやる気があっても雇用者側にも不安や心配があることと、職場配置にも気配りがあったにしても同僚からの偏見によって、仕事ができなくなることが多い。しかしながら何事にも甘えず、一生懸命努力したいと思っています。
(男 26才 1種1級)
軽い障害者は、就職も可能な社会になってきた様ですが、重度障害者は、まだまだ無理のようです。しかし、パソコンやパソコン通信が身近になってきたのですから、これらを利用して在宅勤務が可能になれば、素晴らしいと思います。人手不足のいまが、障害者にとって一種のチャンスであるかもしれませんね。最近、私の友達が就職しました。かなり重度障害ですけれど、車が運転できるのと、この頃はかなり多くの会社がパソコンの仕事だけをさせて、他に動き回るようなことはしなくても良くなり、就職の機会に恵まれました。しかし、私のような外出もままなら身では、まだまだ無理ですね。自分のことはさておき、少しずつではありますが、社会も会社も昔に比べたら随分良くなったように思われます。皆さんの活動を感謝すると共に応援歌します。
(女 34才 脳性小児麻痺 1種2級)
やはり働く以上は、健常者と同等に楽しい気持ちで働きたい。たとえ一つしかその会社でできる仕事がないとしても、私は今能率だけで人間を計る作業形態が嫌いで、生活保護を取り内職をしています。能率と人間は関係ないと思っても、企業の中ではそれが通用しません。
(女 44才 水頭病 2種4級)
企業などで働くためには、ある程度の能力が必要なのですが、普通に就業できる人や努力で可能な人たちもいれば、精一杯努力してやっとそのレベルを保てる人、努力してもなかなか難しい人、障害者同士で能力差別をするようなことがないか、と心配です。
(男 33才 両下肢痙攣性麻痺 1種2級)
会話を主体とする営業、管理職にも就けるように専任手話通訳配置をはじめとする情報保証(証)の完備の実現を切実に望む。
(女 27才 高度難聴 1種2級)
車椅子の人でパソコンの仕事をやっていた人がいて、仕事が忙しすぎてじょくそうができてしまった。会社側の理解が必要である。
(男 22才 頸髄損傷 1種1級)
企業が障害者に対し、門戸をあまり開けていないというのはあると思うが、障害者にももう少し、一般の人に負けないという意欲、実力を持たなければ、本当に社会から孤立してしまうと思う。自分を売り込んでいく事も必要!! やはり本人のやる気と努力が大事。
(男 23才 左膝・足首が曲がらない 2種5級)
今までは、どこで仕事を探せばいいのかわからなかったので、こういう所ができるのは、すごく良い事だと思います。結構「無職」というのは、経済的だけでなく、精神的にも負担になっているので、ちゃんとできるかどうか自信はないけど、仕事を持ちたいと思っている人は多いと思います。僕の場合は在宅でないと、外に出るための支度をしてもらう人やその場所まで連れて行ってもらう人を見つけなければならないし、座ってやるよりベット上でやる方が効率がよかったりすることもあります。(キーボードを打つ事など)
(男 24才 頸髄損傷 1種1級)
自宅でプログラムを組む場合にアドバイスなどのサポートがほしい。
(男 35才 頸髄損傷 1種1級)
もっと多様な雇用形態があってもよいのではないか。もっと時間にフレキシブルな勤務形態も含めて、企業と障害者一人一人を障害のレベルに応じてコーディネートしてくれる人材バングを希望します。
(男 47才 頸髄損傷 1種1級)
今、現在アルバイト(パート)を探していますが、「車イス」というだけでイヤがられる。健常者も障害者も同じ人間なので、少しぐらいの設備を備えてアルバイト(パート)をさせてほしい。
(男 18才 四肢障害 モルキオ病 1種2級)
機能的な障害を個人の責任に帰さない社会的な仕組みが必要。例えば、障害者を対等な条件で雇用した場合の企業の負担増を制度的に助成するなど。大臣や企業のトップにも、適正な比率で障害者が選ばれるべきである。障害をのりこえる為の高度な教育保障が必要である。
(男 56才 難聴 1種2級)
社屋内部の改造を必要しない軽度の障害者しか、雇用しない事を職安で申し渡された事がある。
(男 33才 頸髄損傷 1種1級)
現在はパソコン・ワープロ等でできる仕事がかなり多くなってきていると思うので、障害者もこの様な機器を利用し、社会復帰のチャンスが多くなれば幸いです。
(男 40才 頸髄損傷 1種1級)
重度障害者が仕事をするしないは、本人の自由だと思う。しかし、日々の生活の中で何かやりたい、何かしなければ、何かできる事があればという気持ちは多少誰もが感じている事だと思う。それが仕事であれ、趣味であれ、何であれ、我々にはあまりにも選択の幅がせますぎる。
(男 27才 頸髄損傷 1種1級)
能力がある者には、その能力に応じて就労させるべく、国や企業が積極的に取り組むべきである。
(男 22才 頸髄損傷 1種1級)
障害があっても能力のある人は大勢いるし、仕事に就きたいと意欲があれば、自分の障害の程度にあった仕事に就くべきだと思います。私も4年前に足が悪くしてから、最近やっと自分の将来の仕事について考えるようになりましたが、座ってできるコンピュータなら、努力すればできると思い、その方面の仕事に就くため、技術を身につけようと考えました。そんなときに新聞でこのことを知り、こういう活動はとても有意義なものだと思っています。
(疾病による右膝関節機能全廃 2種4級)
勉強をする場所がないため(情報処理の専門校)入校できない。就職できるまでのレベルにならない。
(男 21才 上肢、下肢に麻痺 1種1級)
今回のプロップ・ステーション設立の動き、大変意義があり、喜ばしいことだと思います。障害者と就業という前に、健常者と就業とはどんな関係があるのか。私の考えでは、就業−とは生活のための賃金を得る手段であると同時に、他人から一人前の人間として見られる要素の一つ。そして、何よりもその人自身の充実した毎日を送るための要素であると。それが障害者の就業に関しても、そっくり当てはまると思っています。
(男 25才 頸髄損傷 1種1級)
完全雇用と言っても、やはり健常者との体力の差は大きく、それだけ働く期間が短い。それらの事が加味された障害者の雇用制度の確立を国及び企業に強く望みたい。
(男 41才 頸髄損傷 1種1級)
誰もが平等に雇用される権利があるということはすばらしいが、平等にということは、能力のない者は雇用されないということになるのでは。障害を持った者の能力の判定の基準が問題なのでは?
(男 30才 頸髄損傷 1種1級)
就業うんぬん以前に、まず親の家を出ることと、女をつかまえること。それが切実です。
(男 37才 頸髄損傷 1種1級)
日本もアメリカ並に雇用範囲を広げて欲しい。
(先天性聾唖 1種2級)
促進法で1.6%とあるが、ほとんど未達成。罰則金を払えば、それで済む現状。もっと罰則金を上げれば……。
(頸髄損傷 1種1級)
私は、障害者のために用意されている線路には進みたくない(甘いかもしれないけど)。普通に会社を訪問して試験を受けて体当たりしたい。雇ってくれるまで何度もトライ!
(頸髄損傷 1種1級)
私たちのまわりには頸損者が仕事できるところがまるっきりと言っていいほどありません。やはり、今回のような企画は、私たちにとっては願ってもないことです。
(頸髄損傷 1種1級)
障害者がそれぞれの能力を無理なく生かせる職場には、今の日本では非常に難しいと思う。将来的には、アメリカのように障害者の人権を法律で総合的に保障することが必要である。その中の一要素として就労があるものと思う。
(匿名)
現在の障害者は(日本では)仕事をしたいと思っている人も含めて“障害者だから”という甘えの考えがある人が多いのではないでしょうか?
(頸髄損傷)
自宅で少しでもできる仕事があれば、生きがいにもなるので良いと思うが本人はそれが逆に家族の者に負担をかけるようになることが心配である。そのためには、ホーム・ヘルパーの派遣制度を確立してほしいと思う。
(頸髄損傷)
大学在学中にいろいろ就職活動をしたが、たいへん難しかった。現在の視覚障害者、特に一般企業への就職状況は、健常者のそれに反し、極めて恵まれたものではないだろう。また、教員その他を見ても、健常者の方が何かと有利であるとも思える。これは、受け入れ側の理解度の未熟さも、それだけではなく、我々もどの程度就業意欲があるのかという点も見過ごすことはできない。閉じ込もりがちになったり、また障害者だけの世界にだけ、しがみついているのではなく、我々ももっと積極的に行動を起こす必要があるのではないだろうか。そして我々も少しでも視野を広げてこそ、道は開けてくるのではと考える。
(25才 視覚障害 1種2級)
今は就労できる人ではなく、知的障害者とか重度の全面介助を要する人の就労をどうとらえるかの時代と思います。
(男 50才 聴覚障害 1種2級)
コンピューターは知的な障害のない人にとっては最高の仕事だと思う。通勤できない人は、在宅でできるよう通信回線を企業で準備して欲しい。
(男 31才 頸髄損傷 1種1級)
障害者としてではなく、一般人として普通に就業する事を希望します。職場には男性、女性、年配、若者がいるように普通に障害者がいることが、最も望ましい社会の状態だと思います。
(女 27才 ギランバレー症候群 1種3級)
会社は社員に単純に労働力だけを求めはしない。会社の掃除もして欲しいし、お茶もいれて欲しいし、忘年会にも出て欲しいし、運動会も参加させたい。また本人の性格的な明朗さ等も要求されて、そしてそれを全部ひっくるめて企業は採用するだろう。その点、障害者は分が悪い。対抗するには健常者に負けない高い仕事の質を供給することしかない。そういった技術を身につける機会を多く与えてもらえれば、雇用の幅も広がるだろう。
(男 26才 内部障害、腎不全 1種1級)
できる仕事の範囲は限られているかも知れないが、可能なかぎり希望の職種にみんなが就けるようになればいいと思う。
(男 20才 二分脊椎 1種1級)
企業と障害者の対話する機会をもっと多くしてください。
(男 28才 1種1級)
障害者といえども、就労、その収入によって生活を営んでいくのは自然な姿だと思うが、それによって頚髄を痛めるなどの二次障害を起こすのではなんにもならない。これからは、この点にも注意して障害者の労働について考えていくべきだと思う。
(男 40才 脳性麻痺 1種1級)
今までの就労形態とは違った形を考えていかなければならないのではないか(例えば、自宅勤務と週何回かの出社)。障害者用の自助具や環境コントロール装置の開発(例えば、介助なしで仕事ができる会社内の設備、作業のリレーをスムースにできるパソコンの開発)。専用住居の確保と通勤手段整備。会社の近くに車椅子用の住居の確保や通勤用の車の運行。
(頸髄損傷 1種1級)
学校を卒業して以来、求職活動を続けてはおりますが、点字図書館などでのアルバイトをしただけで、就職には結びつかなかった。私が求職活動を始めた10年前に比べると、環境は明らかに改善されてきている。雇用促進法に伴う公的職業斡旋制度の定着や補助機器(サポート付きワープロ等)の開発が、雇用を生みだしたことは確かだ。ところが、我々も企業側もお互い相手の事情は良く知らない。間に入った安定所も同じことで、ワープロで作った履歴書を見せたところ、ワープロの仕事をいくつか紹介してくれたが、原稿を起こすようなもので、とても仕事といえる収入にはならなかった。私は、昨年まで盲導犬を使い、その犬の面倒を見ていたし、アパートで自炊、料理、洗濯もし、普通の生活をしている。障害者と企業との間にたって、企業側には障害者の使い方を、障害者には適切な職業指導をするようなシステムがぜひ必要だと思う。
(32才 視覚障害 1種1級)
|